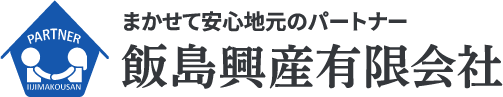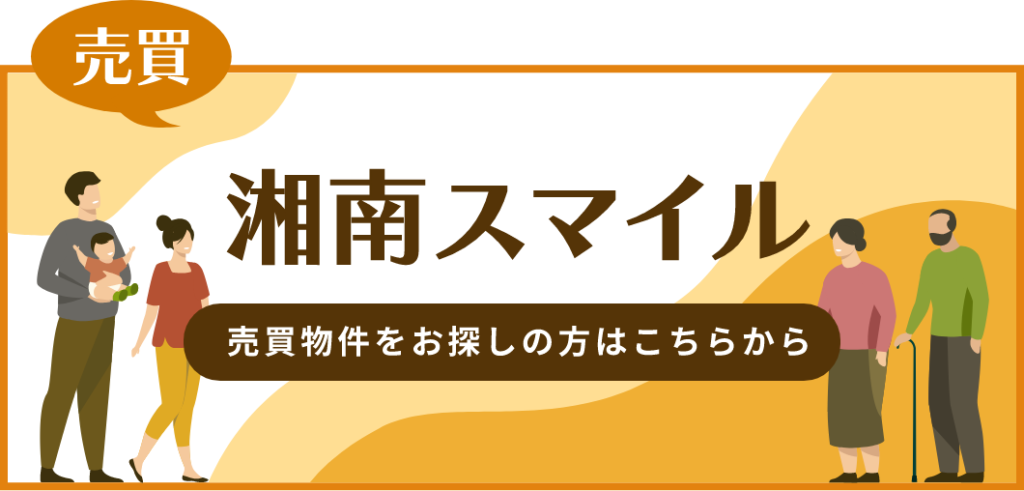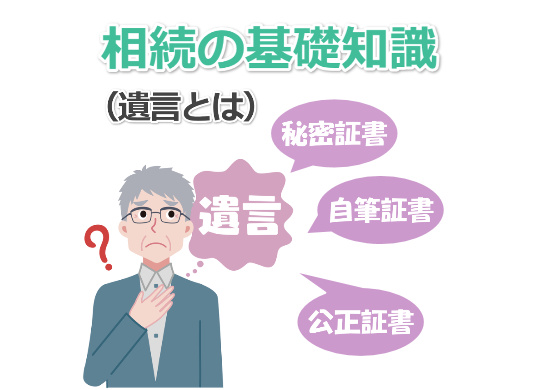
目次
- ■ はじめに
- ■ 遺書と遺言書
- ■ 遺言でできること
- ■ 遺言に必要な能力
- ■ 遺言の性質
- ■ 遺言方式と種類
- ■ 遺言の撤回
- ■ まとめ
■ はじめに
死亡した人の生前の最終の意思を尊重して、死後にその法的効力を認めることを遺言制度といいます。
自分の生存中は望まないが、死後に自分の家を同居中の内縁の妻に与えたいとか、子の認知をしたいとか思った場合には法律上定められた方式に従ってその意思を表示しておけば死後に効力が生じます。
遺言は死亡を契機として効力が生ずる点で相続と類似していますので民法における相続編に定められていますが、相続は財産上の権利・義務の承継に限られるのに反して、遺言はそれだけではなく身分上の行為も含まれますので両者が完全に一致するわけではありません。
今回は、遺言の1回目として「遺言とはどのようなものか」について、基本的な概要をわかりやすくお伝えします。
■ 遺書と遺言書
遺書と遺言書を同じものと認識されがちですが両者には明確な違いがあると言えます。
遺言書は遺産の分け方を示した法的な書類ですが、それに対して、遺書は自分の気持ちを記した手紙のようなものであり、法定効力は生じません。
※遺書が遺言書としての要件を満たしている場合は遺言書として効力が生じます。
■ 遺言でできること
遺言書でできることは法律で認められた一定の事項となります。
①誰に何を渡すのかを指定することができる(相続分や遺産分割方法の指定)
遺言書で誰に何をどのくらい渡すのか明示することが可能です。遺言書であれば法定相続人ではなくとも、お世話になった人などに財産を譲ることも可能となります。
②相続する権利を剥奪が可能(相続人の排除)
本人が特定の相続人から虐待や侮辱などの被害を受けていて、その方に財産を渡したくないなどの場合、その相続人から相続する権利を剥奪することができます。どんな場合でも剥奪できるわけではないため、専門的な知識が必要です。
➂遺言執行者を指定できる(遺言執行者の指定)
遺言書の内容を執行する人を指定することができます。遺言執行者を指定しておくことで相続手続きを速やかにおこなうことができるでしょう。
④子の認知、未成年者の子の後見人指定等
この他にも、あまり知られてはいませんが、保険金の受取人を変更できたり、信託の設定ができたりと遺言書には様々な活用方法があります。遺言書作成のプロに依頼をするとトラブルになりやすい部分にも考慮した遺言書ができるため手の一つです。
■ 遺言に必要な能力
1.遺言能力が認められる2つの要件
各遺言の方式に従って作成されていても、その遺言が無効となってしまう場合があります。それが、遺言者に遺言能力がないと判断された場合です。
遺言能力が認められるには、①満15歳以上であること②意思能力があることが必要です。
①満15歳以上であること
遺言は、代理で行うことができませんので、通常の場合と異なり、親などの親権者が代理することもできません(遺言代理禁止の原則)。一方で、遺言には、未成年者等の行為能力制度の適用もありません(民法962条)。そこで、民法は、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」(民法961条)としています。15歳未満であれば、親の同意があろうがなかろうが、遺言はできない(無効)ですし、15歳に達した者は、親の同意があろうがなかろうが遺言ができる(有効)としています。
②意思能力があること
遺言を行った当時、医者から認知症(の疑いがある)と診断されている場合などに、遺言能力(意思能力)がなく、無効となる可能性があります。
意思能力がないと疑われる場合には、遺言者が成年被後見人となっているケースもあるかと思います。遺言は代理で行うことができませんので、後見人が代わりに行うということももちろんできません。この場合には、下記の特別な形式での遺言でない限り無効とされます。
民法第973条(成年被後見人の遺言)
1 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
■ 遺言の性質
①要式行為
遺言は民法に定める方式に従わなければ、その法律上の効果を生じさせることができず、方式に違反する遺言は無効となります。
②単独行為
ひとつの意思表示により成立する法律行為です。
つまり、被相続人(亡くなった方)の意思表示によって成立し、相手方(遺贈における受遺者など)の意思表示などの行為を要しません。
これに対して、死因贈与契約は贈与者と受贈者の双方の意思表示が必要です。
※ただし、遺言による受遺者は、遺贈を受けるかどうかは、自分の意思で自由に決めることができます。
③死因行為
遺言は遺言者の死亡によって、その効力が生じます。
④代理に親しまない行為
未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人が遺言をする場合であっても、その保護者は同意権や取消権を行使することができません。
■ 遺言方式と種類
遺言には、普通方式遺言と特別方式遺言があり、特別方式遺言は通常使用されることはなく、普通方式遺言が一般的です。
●普通方式
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
●特別方式
一般臨終遺言
難船臨終遺言
伝染病隔離者遺言
在船隔絶地遺言
①自筆証書遺言
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。一見すると最も簡単かつ無料で作成できますので手っ取り早いように思われるかも知れません。しかし、一般の方が自筆証書遺言を書くと、内容が不明確であったりして、法律上無効となる恐れもあります。また、自筆証書遺言は、遺言者の死後、家庭裁判所の検認が必要になってくるため、手続きが煩雑です。なお、家庭裁判所の検認があったからといって、無効な遺言が有効になるわけではありません。
また、自筆証書遺言は、被相続人の死後、相続人が遺言の存在を知りながら遺言書を隠したり、無視したりして、遺言が日の目をみないリスクもあります。
②公正証書遺言
公正証書遺言は、まず本人が公証人役場に出向き、証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。次にこの証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。そして本人と証人で共に署名捺印して作成します。言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されており、オンライン検索も可能になっていることから、その存在が一番確実なものであるため、家庭裁判所における検認手続も不要になります。
③秘密証書遺言
秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。秘密証書遺言は、遺言書の存在は公証人や証人が知るところとなりますので一見確実そうですが、遺言書の内容自体については公証人が確認していませんので、不明確な内容であったりして、法律上無効となる恐れもあります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
特別な方式による遺言
特別な方式による遺言には、一般危急時遺言・船舶遭難者遺言・一般隔絶地遺言・在船者遺言があります。ここでは「一般危急時遺言」をご紹介します。
作成要件
(1) 3人以上の証人が立会い、そのうちの1人に遺言の趣旨を口授(口がきけない人の場合は通訳人の通訳)する。
(2) 口授を受けた証人がそれを筆記する。
(3)口授を受けた証人が、筆記した内容を遺言者及び他の証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
(4) 各証人が、筆記が正確であることを承認した後、遺言書に署名押印する。
なお、遺言の日から20日以内に、証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に請求して遺言の確認を得なければ、一般危急時遺言は効力を生じません。家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得た場合に、確認を行います。また、この遺言は、遺言者が普通方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存するときは無効となります。
■ 遺言の撤回
民法1022条では、一度作成した遺言の一部または全部を撤回することが認められています。
遺言は人の意思の最終」の意思を尊重する制度ですので一度有効な遺言書を作成した後でも遺言者は生前にいつでもその遺言を撤回することができます。
ただし、その撤回は遺言の方式に従わなければなりません。
(遺言の撤回)
民法1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
※ 人の最終の意思を尊重するという遺言制度の趣旨からも自由に撤回が認められます。例えば遺言の中で、撤回しない旨を記載してあっても、その記載は無効となります。つまり撤回権の放棄は認められていない、と言うことです。
※ 遺言を撤回したい場合、「遺言を撤回します」という遺言書を新たに作成することになります。撤回も一種の遺言となります。それ自体を遺言の方式に従わなければなりません。
公正証書で作成した遺言を自筆証書による遺言の方式で撤回することも可能です。また、その逆もできます。方式とは無関係に「常に最新の日付の遺言書が優先される」ことになります。
※ 自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、手元で保管している遺言書を物理的に破棄すれば遺言を撤回したことになります。
ただし自筆証書遺言を法務局に預けている場合、必ず別の遺言書を作成し、撤回することになります。
■ まとめ
死亡した人の生前の最終の意思を尊重して、死後にその法的効力を認めることを遺言制度といいます。
自分の意思をしっかりと残したい場合には、相続に関する専門的な知識が必要になります。相続人が困らないためにも専門家に相談し、作成されることをオススメします。
参考文献:相続法に強くなる63の知識 財団法人大蔵財務協会
■記事の投稿者 飯島興産有限会社 飯島 誠

私は、予想を裏切るご提案(いい意味で)と、他者(他社)を圧倒するクオリティ(良質)を約束し、あなたにも私にもハッピー(幸せ)を約束し、サプライズ(驚き)のパイオニア(先駆者)を目指しています。
1965年神奈川県藤沢市生まれ。亜細亜大学経営学部卒業。(野球部)
東急リバブル株式会社に入社し、不動産売買仲介業務を経て、その後父の経営する飯島興産有限会社にて賃貸管理から相続対策まで不動産に関する資産管理、売買仲介、賃貸管理を行う。
コラムでは不動産関連の法改正、売買、賃貸、資産管理について、実務経験をもとにわかりやすく発信しています。

●資産管理(相続・信託・後見制度)につきましては、こちらをご参照ください。
#不動産 #相続 #相続の基礎 #民法 #相続編 #親族 #姻族 #配偶者 #血族相続人 #相続欠格 #相続人の廃除 #直系尊属 #直系卑属 #嫡出子 #非嫡出子 #半血兄弟 #全血兄弟 #遺言 #公正証書 #直筆証書 #秘密証書