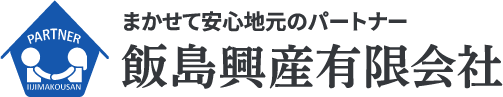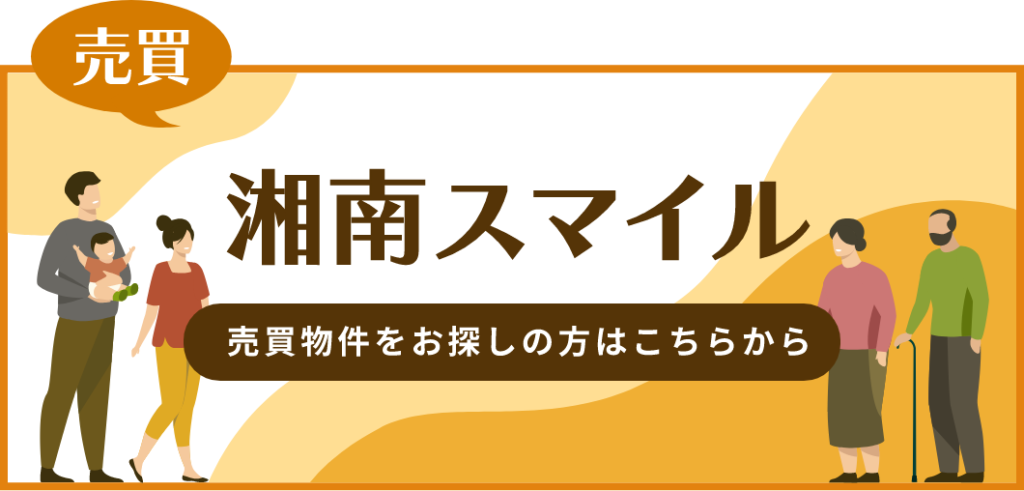執筆者プロフィール
弁護士 渡辺 菜穂子
虎ノ門法律経済事務所に在籍。不動産、遺産相続、借金問題・債務整理、離婚・男女問題、労働問題・労務管理、企業法務の分野で活動を行っている。「ご依頼を受けた案件は、綿密な打ち合わせや準備をしたうえで、判例や法律文献を徹底的に調査し、満足いただける最善の結果を出す」をモットーに、弁護士活動を行っています。

- 1.はじめに
- 2.定期借家契約
- 3. 定期借家契約は、賃貸人にとって本当に使いやすい契約?
- 4. それぞれの段階での注意ポイント
- ① 契約成立段階の注意
- ② 普通借家契約から定期借家契約への切り替え
- ③ 再契約をする場合
- ④ 契約終了段階
- 5.まとめ
1.はじめに
建物の賃借人は、借地借家法によって手厚く保護されています。
このため、賃貸人は、一度借地借家法の適用のある「普通借家契約」を締結してしまったら、契約後に、自分の都合で契約を終了させたいと思っても、そう簡単に賃借人に建物明け渡しを求めることはできません。
たとえ契約書に、契約期間を定めたとしても、契約期間満了時期の6か月前には更新拒絶通知を出さなければなりませんし、またこれらの通知にあたっては、必ず、法律上の「正当事由」がなければなりません。「正当事由」があると裁判所に認めてもらうことは、必ずしも容易ではなく、正当事由が十分でなければ、一定の立退料を支払わなければならない場合もあります。
最近の首都圏内での立ち退き請求事案では、昨今の不動産価格の高騰により、立退料額が高額化する傾向もあり、賃貸人にとっては頭が痛いところです。
しかし、賃貸人側としても、
「この時期には確実に賃貸借契約を終了させて、賃借人に出て行ってもらいたい」
「自分が使わない一定期間だけに限って、建物を賃貸に出したい」
という事情があります。
こんなとき、賃貸人の希望を実現する手段として利用されるのが、「定期借家契約」です。
2.定期借家契約
定期借家契約とは、借地借家法38条に定められた建物賃貸借の一類型で、更新拒絶通知の有無も、正当事由があるかも、いずれも問題とせず、契約書に定められた契約期間が満了すれば、確定的に契約が終了するという、建物賃貸借契約です。 定期借家契約の場合、通常の建物賃貸借契約(普通借家契約)よりも、契約期間内の中途解約はむしろ厳しく制限されるので、「自分が必要な場合にすぐに契約を終了させたい」というオーナーの希望は実現できません。 しかし、オーナー自らが建物を必要とする時期が、あらかじめ確実に決まっているようなケースでは、普通借家契約よりも使い勝手のよい契約類型といえます。
3. 定期借家契約は、賃貸人にとって本当に使いやすい契約?
これだけ聞くと、定期借家契約の方がいい、と思うかもしれません。
しかし実は、定期借家契約も、それほど単純で簡単なものではないのです。
①契約成立段階
②普通借家契約から定期借家契約に切り替える場合
③再契約をする場合
④契約終了段階
それぞれの段階で、オーナー側は十分注意して、対応していく必要があります。
オーナー側で必要な対応を怠ってしまうと、せっかく定期借家契約をした意味がなくなってしまったり、普通借家契約の場合よりも不利になったりすることもあるのです。
それぞれの段階で賃貸人が注意すべき事項をきちんと理解し、正しい理解に基づいて契約締結・対応をとっていく必要があります。
4. それぞれの段階での注意ポイント
① 契約成立段階の注意
普通借家契約ではなく「定期借家契約」が成立した、と認められるためには、契約書に「定期借家契約」「更新しない」と記載するだけでは不十分です。
法律上は、
ア 契約期間の定め
イ 更新しないという条項
ウ 書面で契約を締結すること
エ 更新がないことの書面による事前説明
の4点が必要です。
ウがあるので「口頭」での定期借家契約は成立しません。
もっとも普通は、アやイの条項を記載した契約書を作成するものなので、ア~ウの要件が問題となることはありません。
問題になりがちなのは、エの要件です。
締結する契約書とは別に、賃貸人は賃借人に、「この建物賃貸借契約は更新がなく、期間の満了によって終了する契約です」という内容を記載した書面を、あらかじめ渡して、説明をしなければならないのです。
あとで「そんな書面もらってないし、説明も受けてない」と言われないために、賃貸人としては、契約書とは別に(契約書案文ではダメだ、とされた例があります)、説明書面を用意し、「この書面を受領して、説明を受けたことを確認します」との文言を入れて、賃借人から署名・押印をもらっておくことも重要です。
定期借家契約など、特殊な契約を締結したい場合は、自分でやらず、専門家に任せた方が安心です。
② 普通借家契約から定期借家契約への切り替え
定期借家契約という類型を知ったら、「今貸している建物も、定期借家契約に切り替えたい」と思うオーナーもいるかもしれません。しかし実はそれほど簡単ではありません。
平成12年3月1日より前から契約している「居住用建物」の切り替えは認められない
借地借家契約法の、定期借家契約の条項が施行されたのは平成12年3月1日です。
この制度が施行される際、制度施行日より前から存在する「居住用建物」の普通借家契約については、同一の当事者間で、同一の建物について定期借家契約を締結することは、当分の間、できないとされたのです。
既に制度施行から20年以上経っているのですが、現在もなお、制限が撤廃されていない状況です。
このため、施行日以前から存在する居住用の普通借家契約について、定期借家契約に切り替える内容の合意をしたとしても、無効とされます。
なお、平成12年3月1日以降に成立した普通借家契約については、きちんと合意さえすれば、定期借家契約への切り替えは可能です。
また、事務所、店舗等の事業用賃貸借契約の場合にも、成立した時期が昔のものであっても、切り替えは可能です。
更新がない点で不利であることを説明して認識させた上で契約する必要
法律上は、切り替えが可能な場合であっても、普通借家契約から定期借家契約への切り替えは、通常は不利な内容への切り替えです。
裁判例では、切り替えが有効であるかどうかについて、
「既に存在している契約を更新せずに、終了させること」
「新しい契約は契約期間満了時に更新がないという点でより不利な内容であること」を、きちんと賃借人が理解していることが必要だとも指摘されています。
したがって、単に、所定の手続をとって作成された契約書を保管しておくだけでなく、契約の切り替えにあたり、事前にやり取りした交渉過程のお手紙・やり取りの内容なども、重要な書類として関わってくる可能性があるため、これらの書面もきちんと保管しておいた方がよいでしょう。
③ 再契約をする場合
定期借家契約を締結した場合、契約期間内の解約は、普通借家契約よりも厳しく制限されます。このため、定期借家契約の契約期間は、2年など比較的短期に設定しておき、再契約条項を入れておくことで、契約期間満了時に同じ内容で再契約をし、事実上更新と同様に扱おうとする場合もあります。
しかし実は、更新と再契約とは全く違います。普通借家契約よりもやや面倒な手続が必要なのです。
再契約の場合もまた、契約書作成、書面交付説明が必要
再契約は、法律上は従前の賃貸借契約とは全く別のものです。再契約後の賃貸借も、定期建物賃貸借契約とするならば、再契約をする段階で、また、当初の契約時と同様に、契約書を新たに作成した上で、書面交付による説明が必要となります。説明が必要ということは、単に契約書の郵送等では足らず、かならず対面や電話等で説明が必要だということです。
敷金、保証金、保証人は再契約した契約には引き継がれない
保証人を設けている場合には、新たな契約書にも再度保証人に署名・押印してもらう必要があります。
普通借家契約の更新のように、敷金・保証金が当然に引き継がれるわけではありません。ただし、一度お金を返還しまた預け入れる、という単なる金銭移動の手続をとるのは面倒です。再契約の際の契約書に、占有開始した当初の時点で締結された契約に基づいて預託された敷金・保証金を、返還せずに再契約による敷金・保証金として引き継ぐという内容の条項を入れておく必要があります。
原状回復条項の「原状」の確認
再契約の契約書にも、契約終了時の明け渡し・原状回復条項を設けるはずですが、その「原状」が、再契約時の「原状」ではなく、賃借人が建物の占有を開始した最初の時点の状態であることを確認する特約条項を入れておく必要があります。
④ 契約終了段階
定期借家契約であるからといって、賃貸人側が何もせずに、契約期間満了と同時に契約が当然に終了する、というわけではありません。
法律上、契約終了時期が近くなった段階で、賃貸人がとらなければならない手続があります。
また、契約期間が満了したのに、賃借人が建物の占有を続けている場合、これを放置してしまうと、「黙示の普通借家契約が締結された」と扱われ、せっかく定期借家契約にした意味がなくなってしまうこともあるのです。
終了通知
定期借家契約の契約期間が1年以上の場合、期間満了の1年前から6か月前までの間に、賃貸人は賃借人に対して、期間満了により契約が終了するという内容の通知(終了通知)をしなければなりません。
終了通知は、特に書面で行う必要はないのですが、契約書に「書面で通知する」と書いてある場合には、必ず書面で通知しなければならず、口頭での通知は、要件を満たさないものとされます。
もっとも、定められた期間内に終了通知をするのを失念してしまっても、契約期間満了と当時に、賃貸借契約は確定的に終了します。契約終了に基づく具体的な請求(明渡、遅滞による約定損害金の請求)が、終了通知から6か月経過した後でないと要求できない、ということなのです。
契約期間満了時期と同時に、明け渡しや明け渡し遅滞による遅延損害金の請求をするのであれば、定められた期間内に終了通知を行う必要があります。この期間内の終了通知ができなかった場合であっても、通知時期が、契約期間内か契約期間後であるかに関わらず、通知を行ってから6か月経過すれば、賃借人に対し、契約終了による明渡請求や、約定遅延損害金の請求もできるようになります。
契約期間満了後も使用継続を放置して黙認している場合
定期借家契約の契約期間が終了した後も、賃借人がそのまま使用を継続し、従前と同じように賃料が支払われているとしても、基本的に、それだけで「更新された」「再契約した」「普通借家契約に切り替わった」と扱われるわけではありません。
民法619条1項には、「期間満了後に賃借人が使用継続する場合に、賃貸人がこれを知りながら異議を述べない場合」の黙示の更新の定めがあるのですが、定期借家契約については、「更新はない」とした制度趣旨に鑑み、この民法規定の適用はないとした裁判例もあります。
とはいえ、契約終了後の使用継続をいつまでも放置したり、建物賃貸借契約の継続について賃借人に期待させるようなことをすると、話は変わってきます。
先ほどの「終了通知」の考え方からすると、契約期間満了後、終了通知を行えばその6か月後には明け渡しが求められる、ということになります。しかしそれをいつまでも許してしまうと、「定期借家契約」を一度締結しさえすれば、契約期間満了後は、賃貸人が、いつでも自由に、6か月で契約終了を主張できるという、都合のよい契約類型を作り出すことを認めてしまうことになりかねません。このような法の潜脱のような事態は許されない、ということです。
つまり、裁判例の中には、「定期借家契約が終了したあとも、賃借人が使用を継続し、賃貸人も異議なく賃料を受領し続けている場合には、新たな普通借家契約が締結されたというべきだ」と判断したものもあるのです。
新たに締結されたと判断されるのは、定期借家契約ではなくあくまで普通借家契約です。黙示的な契約ですから当然、契約期間の定めもないですし、更新料の請求などもできません。このように認定されてしまった契約を終了させることは相当ハードルが高くなり(借地借家法に基づき正当事由)、せっかく定期借家契約を締結した意味もなくなってしまうのです。
普通借家契約が締結されたといわれないために
裁判例が、黙示の普通借家契約が締結されたと判断するような事例は、放置・黙認以外にも何らかの事情があるケースですが、とはいえ少なくとも1年以上何もしないということは避けるべきです。
したがって、賃貸人としては、
①適宜の時期に書面で終了通知を行う
②契約期間満了後、すみやかに明け渡しを求め、かつその請求は、内容証明郵便などでその証拠が残る形で行う
③賃借人が応じない場合には、何度も定期的に立ち退きを求める
④少なくとも1年以上放置はしない
⑤新たな定期借家契約締結の打診など、将来の使用継続を期待するような行動はしない
⑥いつまでも明け渡しが実現しない場合は、調停・訴訟など法的手続をとる
など、賃借人側が「いつまでもここにいられる」と期待しないように、様々な対応を積極的にとっていく必要があります。
⑥の段階ではもちろんですが、揉めそうな場合には、早い時期に専門家へ相談するなどして、対策をとっていく必要があります。
5.まとめ
定期借家契約は普通借家契約と違い、賃借人を保護する面が弱い制度です。賃貸人が貸し出す期間を限定的に設定することが可能であり、賃料の値下げに応じる必要はないため、賃貸人にメリットが多い契約といえます。
契約時から定期借家契約を締結する場合は、賃借人も理解したうえで契約を締結するため問題ありませんが、普通賃貸借契約から定期借家契約に切り替える際は注意が必要です。

●資産管理(相続・信託・後見制度)につきましては、こちらをご参照ください。
#弁護士 #弁護士コラム #コラム #定期借家 #普通賃貸借契約 #賃貸 #賃貸管理