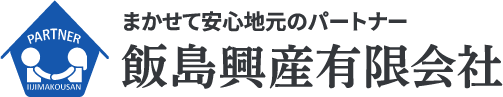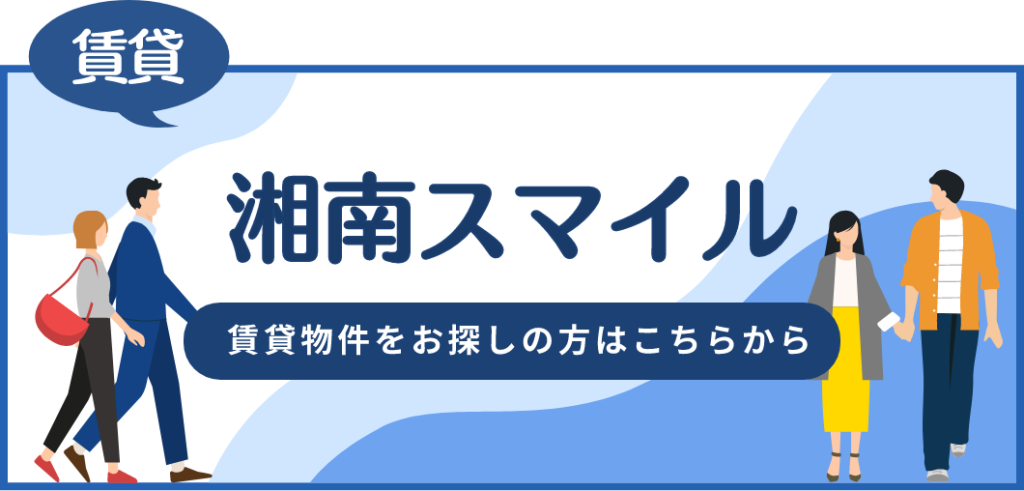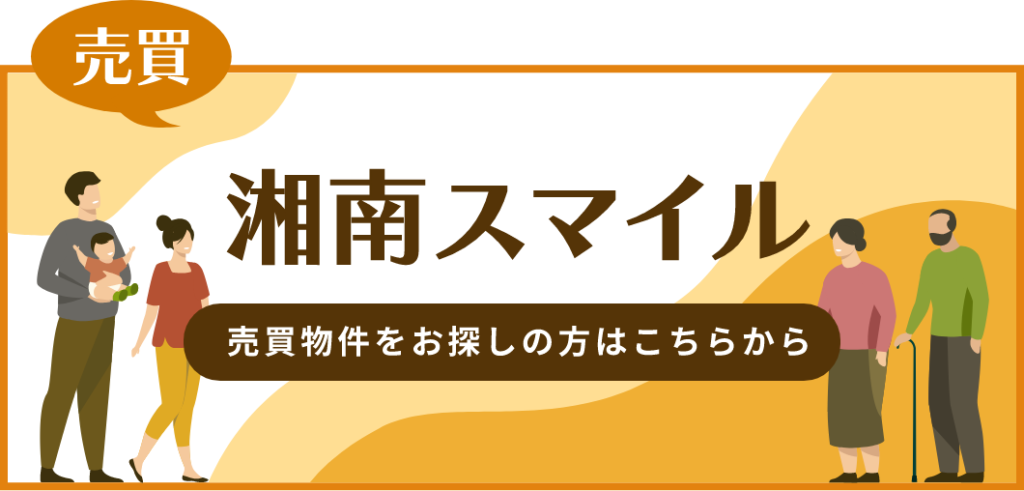目次
- ■ はじめに
- ■ 相続人とは
- ■ 法定相続人が存在しない場合はどうなる
- ■ 特別縁故者とは
- ■ 特別縁故者と認定を受ける場合
- ■ まとめ
■ はじめに
相続が発生した場合、その亡くなられた方の相続財産は、相続人が相続することになります。
一般的に考えて相続人とは、配偶者(妻・夫)、子、孫が考えられ、その家族構成によっては、養子の方が考えられます。
しかし、亡くなられた方に相続人がいない場合、相続財産は誰にわたるのでしょうか。
今回は、相続人とは誰なのか、相続人と呼べるのはどこまでの身内をいうのか、考えてみます。
■ 相続人とは
民法に規定により亡くなられた方の財産を相続するとされていると人のことを法定相続人といいます。
民法では、法定相続人と規定されているのは、配偶者、子、親、兄弟姉妹であり、順位は次のとおりとなります。
第1順位 子ども(直系卑属)
第2順位 親、祖父母(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹(傍系血族)
順位に配偶者が含まれていないのは、民法にて亡くなられた方に配偶者がいる場合、その配偶者は常に法定相続人となります。
順位というのは配偶者以外の場合の順位をいい、上位の法定相続人がいる場合、下位の人は法定相続人とはならない決まりです。
※法廷定相続人が死亡している場合
亡くなられた方の相続が開始する以前に法定相続人が亡くなっている場合、法定相続人の子が代襲相続によって法定相続人となります。
子の代襲相続については直系卑属であれば何代でも代襲相続しますが、兄弟の代襲相続は1代限りです。
亡くなれた方よりも後に孫が死亡した場合、その孫の相続権は孫の子(亡くなれた方から見てひ孫)には代襲相続はされません。理由として代襲相続ではなく、数次相続となります。よって、先に亡くなった孫が被相続人の遺産を相続した形となり、その相続財産を孫の子であるひ孫が相続することになります。
※代襲相続と数次相続の違い
代襲相続
本来相続人となるはずだった人(子や兄弟姉妹など)が、亡くなられた方よりも先に亡くなっている場合、その下の世代(孫や甥・姪など)が代わりに相続する制度です。
数次相続
被相続人の相続人になった人が、亡くなられた方が亡くなられた後で亡くなった場合に発生します。相続人となる孫が、亡くなられた方の死亡後に死亡した場合に該当します。
■ 法定相続人が存在しない場合はどうなる
民法で規定された法定相続人である配偶者、子、親、兄弟姉妹そして代襲相続人であるに孫や姪、甥もいない場合、どのような相続となるのでしょうか。
遺言がある場合
法定相続人が存在しない場合、遺言書の作成により遺言で指定した内容で財産を相続させることが可能です。
※財産を相続させたい相手は、個人だけではなく法人でも可能です。
遺言がない場合
遺言がなく、法定相続人が存在しない場合、相続の手続きは以下の流れとなります。
法定相続人が存在しない場合の遺産は、特別縁故者が取得するか国庫に帰属することになります。
①相続財産清算人を選任する
②特別縁故者がいる場合は特別縁故者が財産を取得する
③特別縁故者がいない場合は国庫に帰属する
※相続財産清算人の選任は、利害関係人または検察官が家庭裁判所に申し立てることになります。この利害関係人とは
①亡くなられた方に金銭を貸していた債権者、
②遺言により特定の財産を譲り受ける人、
③被相続人と生計を同じくしていた人、療養看護に努めた人など、特別な縁故があった人などの特別縁故者。
④相続放棄をした相続人
⑤利害関係人がいない場合などは検察官が申し立てを行う場合もあります。
■ 特別縁故者とは
特別縁故者とは、相続人が存在しない場合、亡くなられた方との間に一定の条件を備えた関係であったことを理由として、特別に亡くなられた方の相続財産を取得できる人のことをいいます。
この特別縁故者の制度は、法定相続人が存在していれば、その法定相続人。亡くなられた方が遺言を作成していれば、その遺言にて指定された人が、相続財産を相続することになります。
しかし、法定相続人が存在しない場合など亡くなられた方の相続財産の受け手がいないことになります。
このような場合、「法定相続人以外の親しかった人などによって取得されるのがなくなれらた方の気持ちではないか」という考えから認められている制度が特別縁故者となります。
特別縁故者と認められるための3要件
特別縁故者と認められるためには、以下の3つの要件のいずれかを満たさなければなりません。
① 被相続人と生計を同じくしていた人
被相続人と生計を同じくしていた人。
たとえば、入籍はしていないものの、事実上夫婦として生活していた内縁の配偶者、同一の世帯に属して生活行動をしていた身内の人などです。
② 被相続人の療養看護に努めた人
療養看護に努めた人も。
たとえば、同居はしていないものの、亡くなられた方の生活の世話、療養看護をしていた人です。
※介護士、看護師、家政婦などは報酬の見返りとして療養看護を業務として行うため、特別縁故者と言えません。
③ その他被相続人と特別の縁故があった者
生計を同じくしていた人や療養看護に努めた人以外に特別な関係にあったと言える人。
※特別縁故者は個人でなく、地方公共団体、宗教団体、学校法人、福祉法人なども含まれます。
※特別縁故者が相続財産を受け取る場合、「相続」ではなく、「遺贈」により取得されることになります。そのため、受け継ぐ財産は相続税の課税対象であり、相続税の申告は、受け取れることを知った日(審判確定日)の翌日から10ケ月以内となります。
※相続税額を計算するの当たり基礎控除として「3,000万円+(法定相続人の数×600万円)」と定められていますが、特別縁故者の場合の控除額は「3,000万円」のみであり、「法定相続人1人あたりの控除額600万円」の部分は適用されません。
※特別縁故者には相続税額の2割が加算されます。
※相次相続控除、障碍者控除、配偶者控除、未成年者控除は適用できません。
■ 特別縁故者と認定を受ける場合
特別縁故者として財産を受け取るためには、自分の勝手で手続きを行うことはできません。この特別縁故者とは家庭裁判所へ特別縁故者の申し立てを行い、認められて特別縁故者となります。
特別縁故者として家庭裁判所に認められるには以下の手続きを行う必要があります。
①相続財産清算人の選任申し立て
初めに家庭裁判所に対し、相続財産清算人の選任申し立てをすることになります。
※特別縁故者として認められたい人は、申し立て権者である利害関係人に含まれるため、申し立てが可能です。
②相続財産清算人の選任および相続人捜索の公告
家庭裁判所より相続財産清算人が選任され、法定相続人の捜索がされます。
この検索は、相続財産清算人が選任された旨や、相続人がいる場合は名乗り出るように官報にて6ヵ月間公告を行います。
※申し立てを行う家庭裁判所は、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
※相続財産清算人は、法定相続人の捜索、相続財産の調査・管理、債権者・受遺者への弁済業務を行うことになります。
※相続財産清算人は、家庭裁判所管轄内にある法律事務所の弁護から選任されます。
③債権者・受遺者に対する申し出の公告
相続財産清算人の選任後、相続財産清算人は、相続債権者および受遺者に対して2カ月以上の公告を行います。
この期間内に相続債権者や受遺者からの申し出があった場合は、被相続人の相続財産から弁済・清算が行われます。
④相続人不存在の確定
相続人捜索の公告期間内に、相続人であることの申し出がない場合、相続人不存在が確定します。
⑤特別縁故者への財産分与審判の申し立て
相続人の不存在確定から3ケ月以内に、特別縁故者は、家庭裁判所に対して、財産分与の申し立てをすることができます。裁判所の審理の結果、特別縁故者であると認められれば、相続財産の全部または一部の分与を受けることが可能となります。
⑥相続財産の国庫帰属
特別縁故者への財産分与を行っても、まだ相続財産に余りがある場合には、最終的に相続財産清算人により国庫に帰属させる手続きがとられます。
■ まとめ
遺言書の作成により、特別縁故者や相続人でなくとも、相続財産を受け取れることが可能です。
また、特別縁故者に認定された場合、相続人以外の人も被相続人の財産の全部または一部を受け取ることが可能です。
しかし、特別縁故者の認定を受ける場合、家庭裁判所への認定手続きが必要であり、認定されない場合もあります。
法定相続人が存在しない場合、相続対策として対策を練ることも重要です。
相続とは、法的な問題などを含むことが多く、早めに専門家に相談されることをおススメします。
■記事の投稿者 飯島興産有限会社 飯島 誠

私は、予想を裏切るご提案(いい意味で)と、他者(他社)を圧倒するクオリティ(良質)を約束し、あなたにも私にもハッピー(幸せ)を約束し、サプライズ(驚き)のパイオニア(先駆者)を目指しています。
1965年神奈川県藤沢市生まれ。亜細亜大学経営学部卒業。(野球部)
東急リバブル株式会社に入社し、不動産売買仲介業務を経て、その後父の経営する飯島興産有限会社にて賃貸管理から相続対策まで不動産に関する資産管理、売買仲介、賃貸管理を行う。
コラムでは不動産関連の法改正、売買、賃貸、資産管理について、実務経験をもとにわかりやすく発信しています。
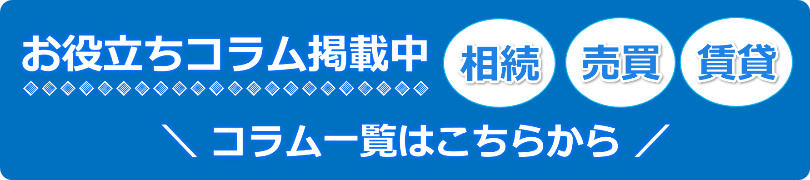

●資産管理(相続・信託・後見制度)につきましては、こちらをご参照ください。
#相続 #相続対策 #相続対策 #特別縁故者 #民法 #家庭裁判所
#法定相続人 #配偶者なし #子なし #兄弟なし