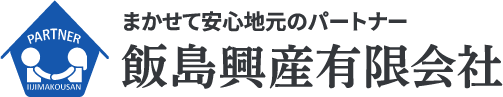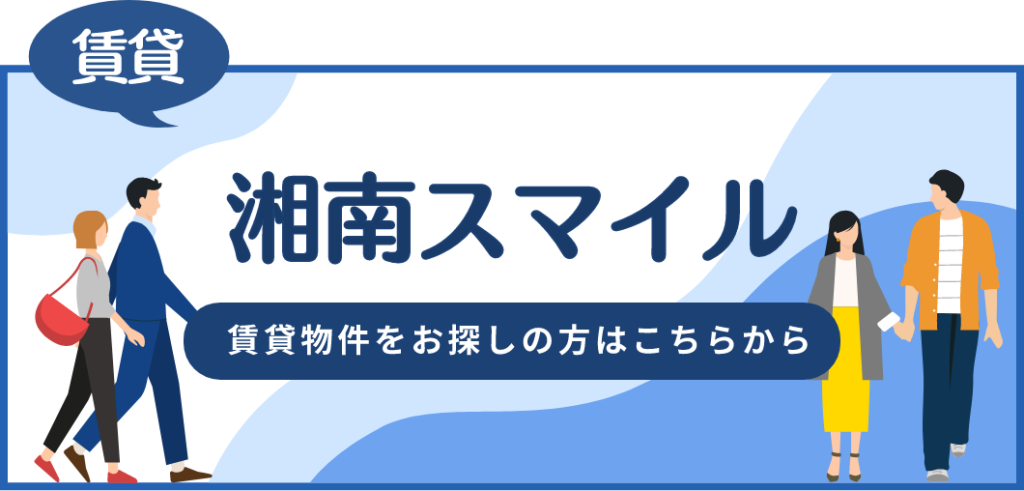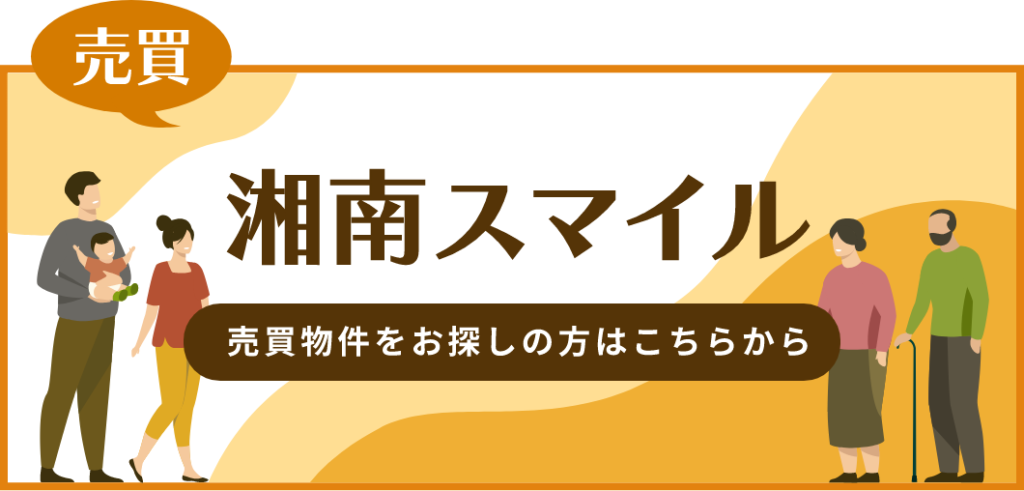目次
- ■ はじめに
- ■ どうして「相続対策」となるのか
- ■ 贈与により「相続税」と「相続」の対策となる
- ■ 贈与前と賃借人を同一人とする方法
- ■ まとめ
■ はじめに
相続税対策として賃貸アパートや賃貸マンションを建築する、言う話を聞いたことがある方も少なないはずです。
この「相続税対策」とした賃貸アパートや賃貸マンションを建築はキチンと手続きを踏めば「相続対策」としても非常に有効なものです。
ただし、キチンと手続きを踏めばと言うことであり、間違った考えでは後で困ることも置きます。
そこで、今回は「賃貸アパートや賃貸マンションを建築するとどうして相続税対策や相続対策」となるのかをサブリース契約と踏まえて考えてみます。
■ どうして「相続対策」となるのか
●根拠
相続税を計算する場合、土地・建物の評価として「貸家建付地」という評価を行うことができ、価格の評価を低くすることが可能です。
相続税の計算において、土地の評価は一律ではなく、その土地の使用方法などにより変わります。これは、国税庁からの通達により、当然に評価を変えることになるのです。
ちなみに「自用地」という用語があります。この自用地、書いて字のごとく「自」分で「用」いる(使う)土「地」であり、自己所有の土地に自宅を建築している場合や月極駐車場として利用している土地のことを言います。
そして「貸家建付地」。「貸家」が「建」て「付」けてある土「地」を言います。
自己所有の土地に自ら賃貸用建物を建築のうえ、第三者に賃貸している土地のことを言います。
その他に「貸宅地」と言うものもあります。
「貸」している土「地」。借地権等の目的として自己所有の土地を第三者に賃貸している土地のことを言います。
その土地を借り第三者は、自らその地のうえに建物を建築することになります。土地を借りた方から見て「借地権」と言われるものです。
●計算方法
貸家建付地の計算方法は、次のとおりです。
自用地評価×{1―(借地権割合×借家権割合×賃貸割合)}が評価となります。
借地権割合は国税庁のホームページの路線価図を閲覧するとその場所の借地権割合が確認できます。
※借家兼割合は、全国一律30%と定められております。また、建物評価額から30%を減額することが可能です。
※賃貸割合は入居率を表す数字ですであり、空室があっても通常の募集を行っていれば問題はありませんが、1年以上空室の場合や募集活動をしていない状況であれば空室の割合が対象されない場合もありますのでご注意ください。
計算例
自用地評価が5,000万円の土地に借地権割合が60%、賃貸割合は問題なしの場合
5,000万円×(1-0.6×0.3×1)=4,100万円
簡単に言えば、18%相続税評価が低くなるということです。
※相続する土地にもよりますが、貸家建付地の評価の他「小規模宅地の特例」、土地面積が500㎡を超え、要件が満たされれば「地積規模の大きな宅地の評価」という評価方法も適用することが可能です。
■ 贈与により「相続税」と「相続」の対策となる
アパート・マンション等を建築し、土地・建物が親名義の場合、建物を子に贈与(全部・一部)した場合、賃貸収入の全部または一部を子に移すことが可能です。
しかし、この場合、相続税評価は、どのようになるのか、心配なところです。
この場合、建築当初の建物所有者は土地の所有者である親であるため、建物の所有者である親と建物の賃借人との間で締結された賃貸借契約にもとづき、建物の賃借人は建物敷地の利用する権利(利用権)を有していたことになります。
敷地利用権は、判例により建物が第三者に譲渡された場合においても、侵害されることはないとされています。
よって、賃貸している建物の所有者に変動があったとしても、新たな建物所有者の敷地利用権が使用貸借に基づく使用借権となり、従来の建物所有者の敷地利用権とは異なるものになった場合でも建物所有者の変更以前に有していた建物賃借人の敷地利用権まで変動したと考えることはできないのです。
この親から子への贈与の場合、贈与前と同一の賃借人が建物を賃借している場合については、土地所有者は建物の敷地についても引続き処分や利用が制限されることになります。
結果、建物とその土地の所有者が同一人であり、その建物が第三者へ賃貸されて、その後建物だけが贈与し、建物の敷地について使用貸借が行われている状況で、その土地について相続があった場合、土地の相続税評価額は、貸家建付地として評価することになります。
ただし、贈与前と賃借人が同一人の場合となります。
では、贈与前と貸家の借家人が異なる場合はどのようなるのか。
建物の贈与後において賃借人に変動があった場合、異動した借家人に係る敷地は自用地として評価されますので注意が必要です。
■ 贈与前と賃借人を同一人とする方法
贈与前と賃借人を同一人とする方法として不動産会社や同族会社と一括借り上げ(サブリース)契約を締結する方法があります。
この場合、子に贈与する前に親が不動産会社や同族会社と一括借り上げ(サブリース)契約を締結した場合、贈与前と賃借人が同一人の場合となります
これは、不動産管理会社などに借家権を与えている状態と解されるからです。
ただし、一括借り上げ(サブリース)を行う会社が同族会社の場合、入居者の募集を実際には行っていない、また、他社に再委託しているなど、実体を伴わない場合は租税回避行為とみなされ、貸家建付地としての評価は受けられなくなります。
実体を伴わない場合は租税回避行為とみなされためには、
・同族会社の定款・登記簿の事業目的として不動産賃貸業、不動産管理業を記載する。
・親と同族会社との間で建物賃貸借契約書を作成のうえ、署記名押印を行う。
・賃貸借契約における修繕費用などの負担を契約書に定めておく。
・転借人との賃貸借契約の貸主は、同族会社とする。
・親・同族会社名義の銀行口座を開設し入出金記録を保管する。
を行うことは最低限のことかと思われます。
■ まとめ
税をキチンとして理解して「相続税対策」・「相続対策」を行うことは非常に歓迎されることです。しかし、税における知識は解釈の仕方によっては大変なことになる可能性もあります。
「相続税対策」・「相続対策」を行いたい場合、そこに強い専門家に相談されることをおススメします。
■記事の投稿者 飯島興産有限会社 飯島 誠

私は、予想を裏切るご提案(いい意味で)と、他者(他社)を圧倒するクオリティ(良質)を約束し、あなたにも私にもハッピー(幸せ)を約束し、サプライズ(驚き)のパイオニア(先駆者)を目指しています。
1965年神奈川県藤沢市生まれ。亜細亜大学経営学部卒業。(野球部)
東急リバブル株式会社に入社し、不動産売買仲介業務を経て、その後父の経営する飯島興産有限会社にて賃貸管理から相続対策まで不動産に関する資産管理、売買仲介、賃貸管理を行う。
コラムでは不動産関連の法改正、売買、賃貸、資産管理について、実務経験をもとにわかりやすく発信しています。
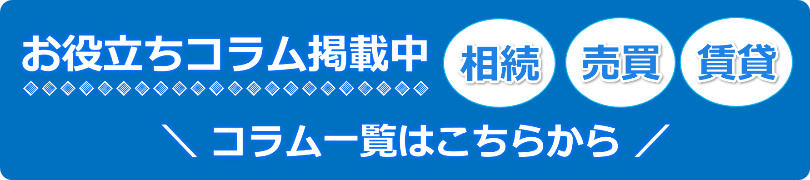

●資産管理(相続・信託・後見制度)につきましては、こちらをご参照ください。
#相続 #相続対策 #相続対策 #アパート建築 #マンション建築 #貸家建付地
#小規模宅地評価 #地積の大きな宅地の評価