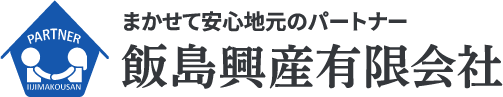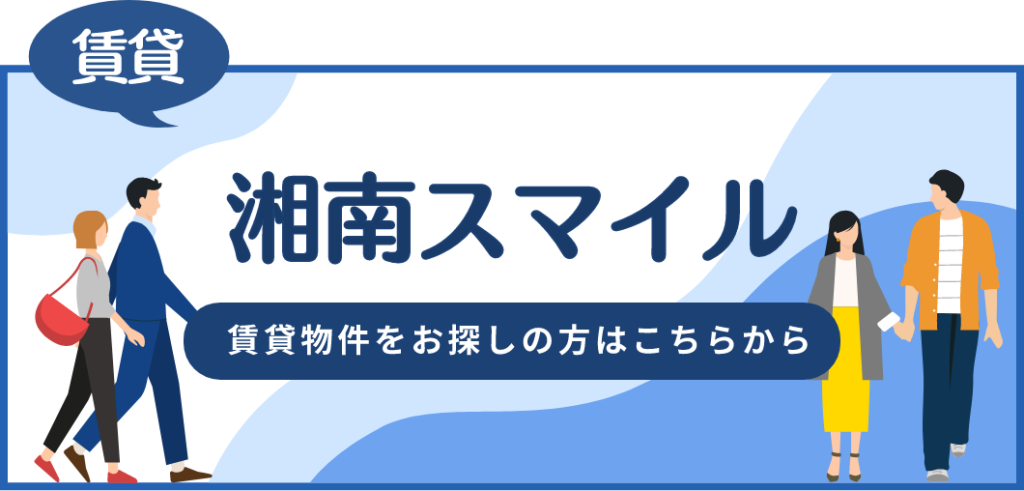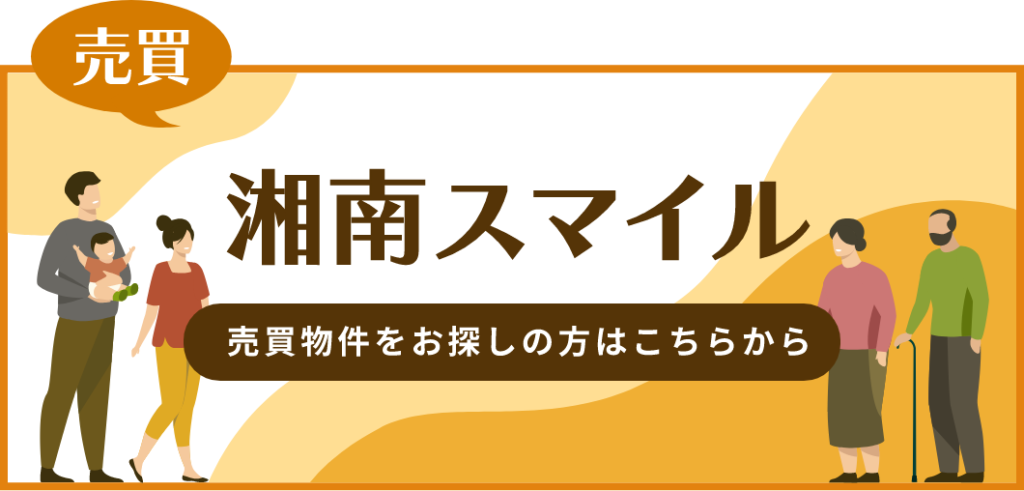目次
- ■ はじめに
- ■ 収益物件の建物を贈与する効果
- ■ 贈与するメリット
- ■ 贈与するデメリット
- ■ まとめ
■ はじめに
相続対策の一つとして不動産賃貸業の法人化の相談を受けることも提案させていただくこともあります。
しかし、賃貸規模や社会保険料の負担等をこう考慮した場合、節税効果や収入の増加が思った程の効果が生じない場合があります。
このような場合、アパートなどの収益物件の建物を贈与する提案があります。
そこで、今回は、相続対策の一つであるアパートなどの収益物件の建物を贈与する場合の注意点などを考えていきます。
■ 収益物件の建物を贈与する効果
相続財産のうちにアパートをいくつか所有している場合、不動産の賃貸収入が親に集中しているはずです。
不動産の賃貸収入が親に集中してしまう場合、所得税のみ考えた場合でもかなり大きな負担が生じているはずです。
所得税は累進税率(5%~45%)のため、所得が増えれば所得税も大きくなります。
そこで、他の家族の所得を確認し、親よりも低い子などへ賃貸収入のある建物を子などに贈与すれば、賃貸収入を子などに移転することができ、親の所得税の負担を減少させることができ、子などの収入も増加させ、相続税も軽減できることになります。
■ 贈与するメリット
収益物件の建物を贈与するメリットとして次の4つが挙げられます。
①贈与財産の評価額が低く抑えられる
収益物件の建物も贈与した場合、贈与税の算出根拠となるのは建物評価額です。
この建物評価額は価格市町村長が毎年4月1日に発表する評価額のことです。
仮に現金5,000万円を贈与する場合、贈与税の課税対象額は4890万円(5000万円-基礎控除110万円)となります。
一方、収益物件の建物を贈与する場合、5000万円で購入したとしても、贈与時の評価額は時価(実勢価格)の55%前後となるため、贈与財産の評価額を下げることが可能です。また、築年数の経過している建物の場合、評価額も低くなっているため、支出を抑えることも可能です。
②贈与後の賃貸収入は贈与を受けた者の収入になる
収益物件の建物を贈与すると、贈与後の賃貸収入は、贈与を受けた者の収入となります。
仮に年間1000万円の収入がある賃貸アパートを贈与した場合、10年単位で考えた場合、贈与しない場合、親には1億円の資産が相続財産として残ることになります。
一方、贈与をした場合、この1億円は、子などのものにすることができ、親が亡くなられた場合、相続税算出の課税遺産総額を抑え、相続税を軽減することになります。
③所得を分散させることができる
収益物件の建物を贈与することにより、親の所得を分散させることが可能であり、所得税の累進税率を下げることになります。
④継がせたい者に贈与できる
収益物件を贈与した場合、継がせたい者に引き継がせることができます。
贈与せず、収益物件を相続されるには、遺言書を作成しない限りできません。
遺言がない場合、相続人同士の遺産分割協議にて取り決めるため、継がせたい者以外に収益物件が相続される場合もあります。
■ 贈与するデメリット
収益物件の建物を贈与するデメリットとして次の4つが挙げられます。
①贈与した者の相続時に土地の相続税評価額が高くなる
収益物件の建物を贈与した場合、贈与をした者の相続が発生した場合、土地の相続税評価額が高くなります。
これは、仮に収益物件がアパートの場合、相続税の不動産評価において「貸家建付地」となり、土地に対し、評価減が可能となります。
貸家建付地の評価 = 自用地としての価額 - 自用地としての価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合
しかし、土地は親、建物は子となった場合、土地に対し、貸家建付地の評価減の適用はできず、自用地としての評価となり、相続税が割高となってしまいます。
しかし、当初は建物所有者である親が土地の所有者であり、贈与をする前からの借家人がいた場合には、その借家人についてはAさんとの間での契約に基づいて敷地の利用権も有していたことになります。
そして、この建物借家人の有する敷地利用権は、判例により建物が第三者に譲渡された場合においても、侵害されることはないとされており、贈与前と同一の借主が建物を賃借している場合は、土地所有者は建物の敷地についても引き続き処分や利用が制限されることになり、自用地評価額から相応の減額を行うべきと考えられています。
以上により、建物とその敷地の所有者が同一人で、その建物が他人に賃貸されており、その後建物だけが贈与されて、建物の敷地について使用貸借が行われている状況で、その土地について相続があった場合の土地の相続税評価額は、貸家建付地として評価することとされます。
②負担付贈与に注意
収益物件を贈与する場合、贈与した者が金融機関より借入れた融資を負担させる場合には「負担付贈与」となります。
負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負わせることを条件に行う財産の贈与をいい、収益物件に金融機関からの借入がある場合、贈与と併せて借入金の負担を負わせる場合は負担付贈与になります。
※通常の贈与の場合、課税の対象となる不動産の評価額を算出する場合、「相続税評価額」となりますが、負担付贈与契約の場合は「時価(市場価格)」となり、負担付贈与の場合、通常の贈与よりも税額の負担分が多くなります。
負担付贈与を受けたときの贈与税の計算では、贈与財産の時価から債務を差し引いた額に対して贈与税がかかります。
この場合、時価とは建物の固定資産税評価額ではなく、通常の取引価額となります。
これにより、贈与税の算出にあたり、贈与税も増えることになります。
また、収益物件の場合、敷金を預かることは一般的であり、借主の退去時に貸主は返還義務があります。
そのため、親が子にアパートを贈与する際に、敷金も引き継ぐ場合、負担付贈与とみなされます。
この対処方法として敷金を引き継ぐ場合、敷金と同額の現金も併せて贈与し、負担額をゼロとして負担付贈与を防ぐことができます。
③不動産取得税などの税負担が多い
収益物件の建物を贈与する場合、不動産取得税が課税されます。
相続による取得の場合には不動産取得税は課税されませんが、贈与の場合、不動産取得税の納税は悲痛用となるため、税負担が増えることになります。
また所有権の移転登記を行う場合、登録免許税について相続であれば固定資産税評価額の0.4%となり、贈与の場合、2.0%となります。
④相続時にトラブルになる場合がある
収益物件の建物などを一部の相続人に贈与した場合、その他の相続人間から「特別受益」を請求される可能性があります。
特別受益とは、被相続人から生前贈与などによって「特別に受けた利益」のことで、相続人間での遺産分割の公平性を高めるための制度です。
生前贈与による特別受益が認められた場合、贈与財産を相続財産に加算して遺産分割をしなくてはなりません。
■ まとめ
収益物件の建物を贈与することはメリットがある一方、デメリットや注意点もあります。
まずは、贈与と相続を比較し、そして暦年課税と相続時精算課税を比較することと他の相続人とのバランスなどを考慮する必要があります。
収益物件の建物を贈与することは相続対策や所得の分散として非常に大きな意味を持つものです。
メリットがある一方、デメリットや注意点もありますので専門家の意見も取り入れながら、最適な選択をされることをおすすめします。
■記事の投稿者 飯島興産有限会社 飯島 誠

私は、予想を裏切るご提案(いい意味で)と、他者(他社)を圧倒するクオリティ(良質)を約束し、あなたにも私にもハッピー(幸せ)を約束し、サプライズ(驚き)のパイオニア(先駆者)を目指しています。
1965年神奈川県藤沢市生まれ。亜細亜大学経営学部卒業。(野球部)
東急リバブル株式会社に入社し、不動産売買仲介業務を経て、その後父の経営する飯島興産有限会社にて賃貸管理から相続対策まで不動産に関する資産管理、売買仲介、賃貸管理を行う。
コラムでは不動産関連の法改正、売買、賃貸、資産管理について、実務経験をもとにわかりやすく発信しています。
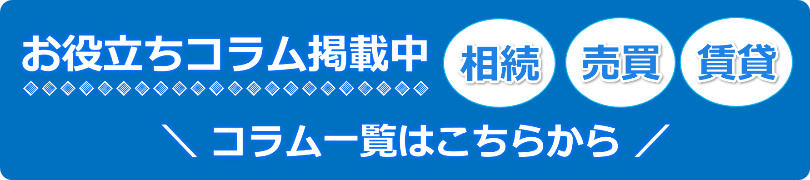

●資産管理(相続・信託・後見制度)につきましては、こちらをご参照ください。
#相続 #相続対策 #建物 #贈与 #建物贈与 #収益物件 #相続? #贈与?