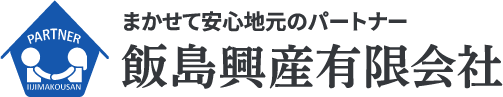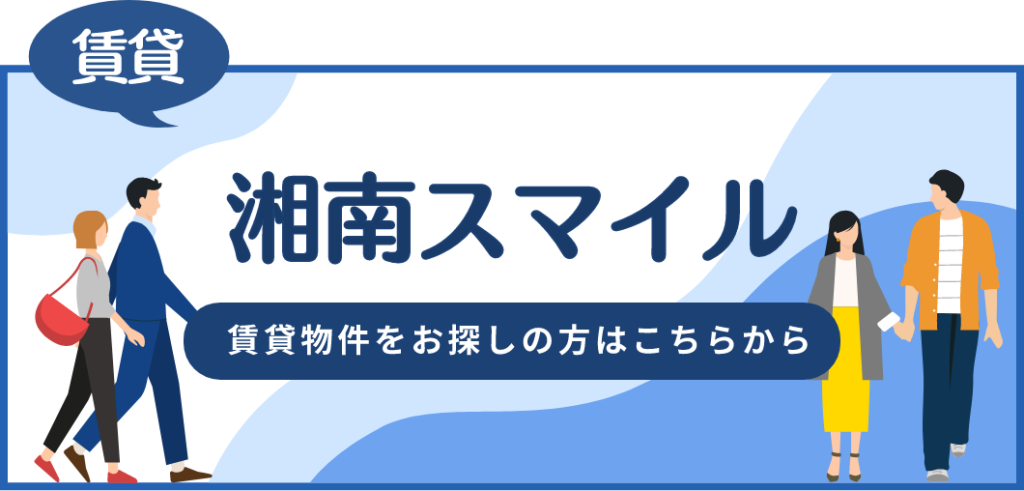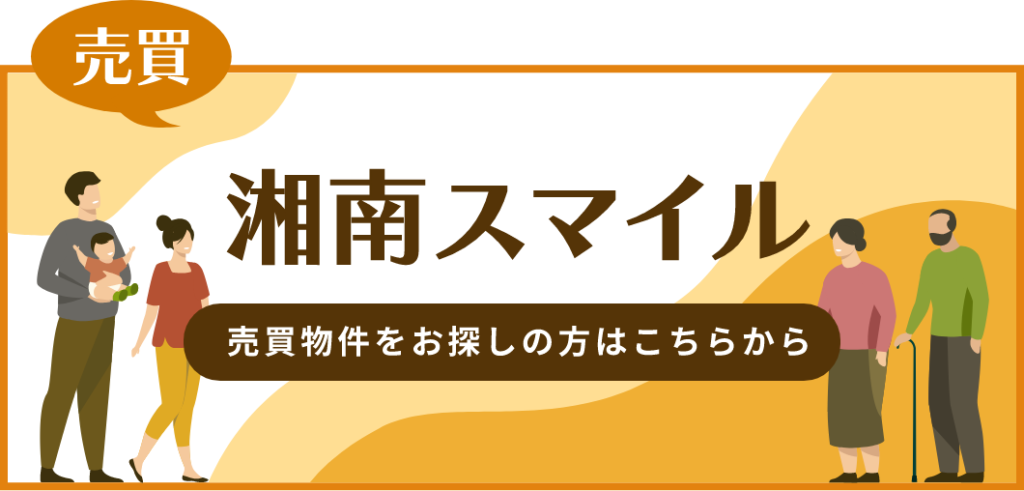目次
- ■ はじめに
- ■ 相続財産に含まれるもの
- ■ 債務控除とは
- ■ 相続税がかかるケース
- ■ まとめ
■ はじめに
相続対策において、相続税対策としてアパートを建築し、金融機関より建築費を借り入れて債務控除により相続税の軽減をはかる、という対策を考えられると思います。
しかし、相続対策としてアパートを建築し、相続税対策を万全と思われていた方も、実際に相続が発生し、相続税を計算した場合、分割方法によっては「債務控除が全額控除できない!」という場合もあります。
今回は、相続税の計算過程において債務控除がどのように軽減されていくのか、また、債務控除が適用できない債務などを考えてみます。
■ 相続財産に含まれるもの
相続財産(プラス財産)
・被相続人が残した預貯金等の相続財産(プラス財産)
1.不動産と不動産上の権利:宅地、農地、建物、店舗、居宅、借地権、借家権など
2.現金・有価証券:現金、預貯金、株券、貸付金、売掛金、小切手など
3.動産:自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品など
4.その他:電話加入権、ゴルフ会員権、著作権、慰謝料請求権、損害賠償請求権など
相続財産(マイナス財産)
・借金や未払いの税金等の財産(マイナス財産)
1.負債:借金、買掛金、住宅ローン、小切手など
2.税金関係:未払いの所得税と住民税、その他未払いの税金など
3.その他:未払い分の家賃・地代、未払い分の医療費など
■ 債務控除とは
相続税の計算において、被相続人が残した預貯金等の相続財産(プラス財産)から借金や未払いの税金等の財産(マイナス財産)を差し引いた額をもとに計算します。
このマイナスの財産を差し引くことを債務控除といいます。
債務控除できる債務は、相続開始日時点で存在する債務で確実と認められるものとされています。
債務控除はその債務すべてが控除されるわけではなく、どれだけの債務が認められるかのより、相続税額も変わってきますので、債務控除の対象を正確に把握することはとても重要です。
【債務控除の対象となる債務】
・連帯債務での借り入れ ・所得税 ・消費税住民税 ・固定資産税 ・未払いの医療費
・未払いの公共料金 ・未払いのクレジットカード代金 ・事業における未払い金や預り金
・葬儀費用
【債務控除の対象とならない債務】
・保証人になっている借り入れ ・団信に加入している住宅ローン ・未払いの墓地や仏壇の購入費用 ・相続財産の管理費用 ・遺言執行費用 ・香典返し ・法事にかかる費用
■ 相続税がかかるケース
【アパート建築における参考例】
被相続人財産 アパート(土地・建物)、預貯金等を含めてその他財産
被相続人:父親 相続人:子(長男、二男)
アパート土地 評価額 5,000万円
評価減 ▲3,000万円 貸家建付地、小規模宅地特例
小規模宅地は考慮しておりません
アパート建物 評価額 5,000万円
評価減 ▲1,500万円 借家権割合
借入金 ▲1億円
その他の財産 8,500万円
差引合計 4,000万円
上記のとおり、アパート建築により、アパート敷地については貸家建付地評価と小規模宅地特例で3,000万円の評価減。
建物の評価は、固定資産税評価になり、貸家としての借家権割合の適用により1,500万円の評価減となります。
その結果、差引合計すると財産合計は、4,000万円となり、基礎控除額4,200万円(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内のため、相続税はかからない、という相続対策となります。
相続税対策として参考例のような提案はよくあることかと思われます。
しかし、相続が発生した場合、アパートの敷地と建物を長男が取得し、その他財産を二男が相続した場合を想定し、相続税の計算をしてみた場合、
長男の財産:5,000万円-3,000万円+5,000万円-1,500万円-9,000万円=▲3,500万円
次男の財産:8,000万円
となります。
相続税の計算方法は、個別に取得した財産を合計して、相続税の課税対象となる額を計算するため、長男が取得した財産はマイナスでゼロと評価され、相続税は課税されません。
一方、二男は8,000万円を相続し、債務控除(マイナス財産)がないため、相続する8,000万円を課税価格として計算します。
よって、基礎控除額である4,200万円を控除した3,800万円に対し、相続税がかかることになります。
相続対策として、相続財産全体を見たうえで、対策を提案しますが、誰がどのように遺産分割されるのかを、加味して検討することが必要と言うことです。
このような事案は、代償金の受渡しでも起こる可能性がありますので注意が必要です。
【相続税法】
(債務控除)
第十三条 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
二 被相続人に係る葬式費用
2 相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第三号又は第四号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一 その財産に係る公租公課
二 その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務
三 前二号に掲げる債務を除くほか、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務
四 その財産に関する贈与の義務
五 前各号に掲げる債務を除くほか、被相続人が死亡の際この法律の施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務
3 前条第一項第二号又は第三号に掲げる財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、前二項の規定による控除金額に算入しない。ただし、同条第二項の規定により同号に掲げる財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。
4 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が当該特別寄与者に係る課税価格に算入される場合においては、当該特別寄与料を支払うべき相続人が相続又は遺贈により取得した財産については、当該相続人に係る課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から当該特別寄与料の額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
この相続税法第13条の規定によると債務控除が可能なのは、相続又は遺贈(包括遺贈又は被相続人から相続人に対する遺贈に限る。)によって財産を取得した相続人の課税価格の計算上において実際に取得する財産の価額から負担する債務の金額を控除するものであり、債務を負担する相続人以外の相続人が取得する財産の価額および相続税法第19条の規定により相続税の課税価格に加算された相続開始前7年以内の贈与財産の価額から控除することはできないとされており、相続人のうち他の債務を負担しなかった相続人の取得財産の価額から控除することはできないことになります。
■ まとめ
相続税を計算するうえで債務控除がどれだけ認められるかにより、相続税も変わりますので、債務控除の対象を正確に把握することはとても重要です。
多額の財産を所有されている方は、アパート建築など相続税対策を行う必要は生じますが、ご紹介したように財産より債務の方が多いのに、相続税がかかること場合も生じます。
相続税対策を行う場合、一つの不動産に対し、どれだけの債務があり、誰が相続するのかを含めて対策を行う必要が生じます。
相続税の対策を行う場合、税金を減らすことに集中してしまいますが、全体を見ながら相続対策を行っていただくことをオススメします。
■記事の投稿者 飯島興産有限会社 飯島 誠

私は、予想を裏切るご提案(いい意味で)と、他者(他社)を圧倒するクオリティ(良質)を約束し、あなたにも私にもハッピー(幸せ)を約束し、サプライズ(驚き)のパイオニア(先駆者)を目指しています。
1965年神奈川県藤沢市生まれ。亜細亜大学経営学部卒業。(野球部)
東急リバブル株式会社に入社し、不動産売買仲介業務を経て、その後父の経営する飯島興産有限会社にて賃貸管理から相続対策まで不動産に関する資産管理、売買仲介、賃貸管理を行う。
コラムでは不動産関連の法改正、売買、賃貸、資産管理について、実務経験をもとにわかりやすく発信しています。
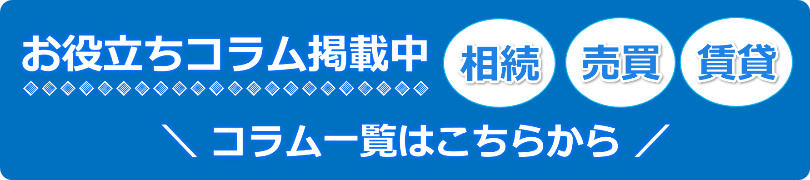

●資産管理(相続・信託・後見制度)につきましては、こちらをご参照ください。
#相続 #相続対策 #債務 #贈与 #債務控除 #プラス財産 #マイナス財産 #相続税法第13条