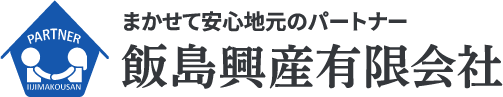2019年に施行された民法改正により、今までは、遺言があると相続が発生しても遺産分割協議が必要ない為、相続手続きが遅れがちでした。しかし、これからは、遺言があっても相続手続き(登記)の遅れにより第三者へ名義が変わってしまう恐れがあります。

遺言や遺産分割協議によって、法定相続割合を超える持分を取得することとなった相続人は、不動産で例えるならばその旨の登記を備えなければ、第三者に対して当該取得持分を主張することができなくなりました。
改正民法899条の2 第1項
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
簡単に言いますと、
相続が発生し、遺言でも遺産分割にしろ法定相続分を超えて財産を相続した場合は、法定相続分を超える部分については、第三者より先に登記しない場合、第三者に先に登記されると主張できません。
ということになりました。
今後、特に遺言によって法定相続分以上の財産を取得する相続人は、他人に権利を奪われないように十分に注意する必要があります。
民法改正前では、遺言書に「長男Aに財産を全部相続させると記載しておけば、遺留分の問題は別として、長男Aは、原則として誰に対してもその権利の取得を主張できました。
しかし、遺言書に力を与えすぎてしまった為、一方で不利益を受ける人もあり、実務上相続人間で争いも絶えなかったのも事実です。
例えば、
父が遺言書で長男Aに「私の財産はすべて長男Aに相続させる」と作成して死亡した場合、
二男Bは第三者であるCから借金があったとします。
第三者であるCは借金を取り立てるために、二男Bが相続した財産を差し押さえて借金の回収に回したいと考えます。
では、この場合第三者であるCは借金の取立てができるでしょうか?
改正以前の民法では、この場合第三者であるCは、長男Aがすべての財産を遺言にて相続するため、父親の財産から二男Bの借金の回収はできません。
理由としては、遺言書の中に「長男Aに全部相続させる」と記載がありますので、長男Aはこれを第三者Cにも主張できるためです。
万一、相続登記が未了の場合でも、長男Aは「財産はすべて私のものだから、第三者であるCがこの財産を差押えするのは筋違い」と主張が可能でした。
このように、遺言書があるからと言って、いつまでも登記をしないでいる相続人を保護して、一方で第三者をないがしろにして良いのか、という議論があり、この度の改正に至ったのです。
第三者であるCから見れば、遺言書の内容がどのようなものかなど知る術がありません。万一、二男Bに貸したものが回収できなくても二男Bが相続した時点で不動産などを差し押さえればよいと考えるはずです。
しかし、遺言により長男Aがすべての財産を相続するとなれば第三者Cの考えを一方的に害することになります。これが今回の改正に至った理由なのです。
そして改正後には、
長男Aが「すべての財産は私のものだ」と主張するのではあれば、第三者Cが差し押さえるよりも先に、相続の登記をしなければならないということです。
改正以前のように、相続の登記を行わなくとも第三者に権利を主張することはできなくなったのです。
今回記載した例のほか、さまざまなケースが考えられます。遺産として不動産を相続した場合に限らず、銀行預金などの債権を相続した場合にも適用されます。
例えば、法定相続分以上の預金を相続した場合は、銀行に対してその旨の通知をしなければ第三者に対して権利を主張できなくなります。この通知は、内容証明郵便など確定日付のある証書でする必要があります。
民法改正にあたり、あまり問題とならなかった改正点ですが、実務上問題が発生してきています。なんでも100%はありませんのでご注意ください。
■記事の投稿者 飯島興産有限会社 飯島 誠

私は、予想を裏切るご提案(いい意味で)と、他者(他社)を圧倒するクオリティ(良質)を約束し、あなたにも私にもハッピー(幸せ)を約束し、サプライズ(驚き)のパイオニア(先駆者)を目指しています。
1965年神奈川県藤沢市生まれ。亜細亜大学経営学部卒業。(野球部)
東急リバブル株式会社に入社し、不動産売買仲介業務を経て、その後父の経営する飯島興産有限会社にて賃貸管理から相続対策まで不動産に関する資産管理、売買仲介、賃貸管理を行う。
コラムでは不動産関連の法改正、売買、賃貸、資産管理について、実務経験をもとにわかりやすく発信しています。
●資産管理(相続・信託・後見制度)につきましては、こちらをご参照ください。