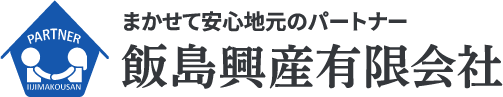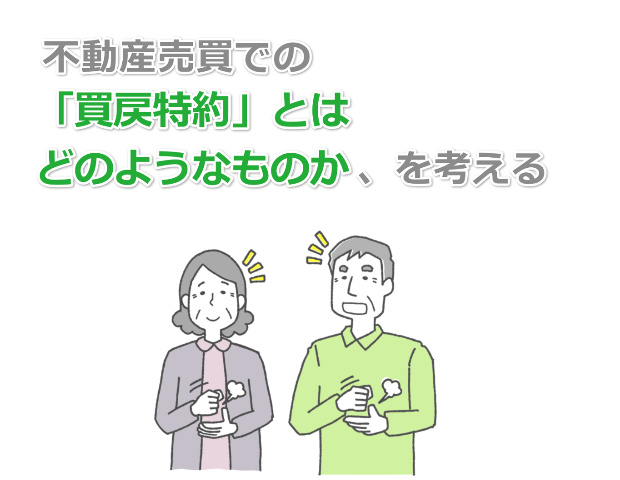
■ 目次
- ■ はじめに
- ■ 買戻特約とは
- ■ 買戻特約が設けられた背景
- ■ 買戻特約の流れ
- ■ 不動産業界での「買戻し」
- ■ まとめ
■ はじめに
「買戻特約」をご存じでしょうか。
現在では見かけなくなってきましたが、バブル期など公団(現UR都市機構など)の分譲住宅・マンションの売買契約書には転売禁止特約。「買戻特約」が盛り込まれていました。
民間のデベロッパーは分譲を行う場合、売却価格には土地代、建築費、広告宣伝費に加えて、利益分が含まれています。
一方、公団(現UR都市機構)や公社は、国民や地域住民への良質な住宅供給という公共的な目的を主としているため、過度な利益を追求せず、原価に近い形で価格設定されることが一般的でした。
そのため、バブル期など地価が上昇している場合、民間のデベロッパーの分譲価格より公団(現UR都市機構など)の分譲価格が下回っていため、転売を防ぐ必要がありました。
現在、東京都心を中心とした地価上昇により転売が繰り返されている状況を踏まえ、今回は、この「買戻特約」について考えてみます。
■ 買戻特約とは
買戻特約とは、売買契約締結後において一定期間であれば売主が売却した不動産を買い戻せるという内容の特約です。
この買戻特約とは、民法にて規定されている有効な方法であり、2020年の民法改正前では買戻金額は「買主が支払った代金及び契約の費用」に限定されていましたが、改正により、買戻金額について当事者間で自由に合意できるようになりました。
また、2023年の不動産登記法改正により、売買契約から10年が経過した場合、買戻し特約の登記権利者は単独で抹消登記を申請できるようになっています。
現行民法(改正後)
(買戻しの特約)
第579条 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
(買戻しの期間)
第580条 買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。
2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
3 買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない。
■ 買戻特約が設けられた背景
公団(現UR都市機構)や公社の分譲住宅に「買戻特約」が設けられた背景には、国民の住宅不足を解消するためであったにもかかわらず、高度経済成長期など、不動産価格が急騰していた時代には、公団から分譲住宅を購入後において第三者に転売するという投機行為が発生することもありました。
そこで、公的な資金や制度で供給される分譲住宅であるため、真に居住を目的とする人々に公平に行き渡るようにする必要があり、買戻特約が盛り込まれるようになったのです。
■ 買戻特約の流れ
公団住宅(現UR都市機構などの分譲物件)における「買戻し特約」の設定は、売買契約と同時に行われ、所有権移転登記と同時に登記されます。買主側で特段の手続きは必要なく、契約時に自動的に設定されるものです。
買戻し特約の設定までの流れは以下の通りです。
・売買契約の締結
買主と売主間で買戻し特約の内容(期間、代金額など)を定めます。
特約が付いた内容で売買契約を結びます。
・登記手続き
所有権移転登記と同時に、買戻し特約の登記を申請します。
・売買代金の支払いと不動産の引き渡し
売主は買主に売買代金と契約費用を支払います。
買主は売主に対し、引き渡します。
・買戻しの実行(該当する場合)
売主が買い戻す意思がある場合、契約で定めた期間内に、買主に売買代金と契約費用を返還します。
買主から売主へ所有権を移転する登記を行います。
・期間満了後の流れ
抹消登記手続きの実施:
買戻し特約は自動で抹消されないため、期間満了後に買主と売主が共同で抹消登記の手続きを行う必要があります。
買主またはその代理人(司法書士など)が、必要書類を作成して法務局に申請します。
手続きをしないと特約が残ったままになり、将来的な不動産売却が難しくなるため、必ず行う必要があります。
※令和5年(2023年)4月の法改正により、売買契約から10年以上経過している買い戻し特約の抹消登記は買主様(現不動産所有者)単独で手続きできるようになっています。
■ 不動産業界での「買戻し」
不動産業界では、「買戻し」というと、民法上の買戻しの他、「再売買の予約」や、「譲渡担保」の意味で使われることもあります。
この「再売買の予約」と「譲渡担保」は、「買戻特約」と同様にその不動産を再び取り戻せるということで混同しないよう注意が必要です。
そこで、「再売買の予約」と「譲渡担保」とはどのようなものか、ご説明しておきます。
再売買の予約
不動産の「再売買の予約」とは、売主が買主に対し、売却した不動産を将来、売主が買い戻すことを事前に約束しておく契約です。
この「再売買の予約」は、融資の担保として利用されることが多く、債権者が不動産の所有権を一時的に取得し、債務者が返済した際に、再度買い戻すという仕組みです。
買戻し特約とは、再度買い戻すという仕組みとして似ていますが、契約と同時に行わなくてもよく、買戻代金や期間を自由に決められ点が「買戻特約」と異なる部分です。
再売買の予約の流れ
・融資の担保として、不動産を債権者に売却します。
・売買の際に、「将来、売主が買主に代金を支払えば、買主がその不動産を売主に戻す」という予約をします。
・予約により、売主は買主の承諾なしに、将来、売買を完結させる権利(予約完結権)を得ます。
・売主が融資を返済できれば、予約完結権を行使して不動産を買い戻すことができます。返済できなかった場合は、買主が不動産を所有し続けることになります。
譲渡担保
不動産の譲渡担保とは、債務の担保として、債務者の不動産の所有権を債権者に形式的に移転する制度となります。
債務の返済が完了すれば不動産の所有権は債務者に復帰しますが、債務不履行の場合は、債権者がその不動産を確定的に取得するか、または売却など処分して債権を回収します。
譲渡担保の流れ
・債権者と債務者の間で、被担保債権を担保するために不動産の所有権を譲渡する契約を締結します。
・債務者が不動産の所有権を形式的に債権者に移転させるため、譲渡担保権設定者と譲渡担保権者が共同で法務局に申請します。
・債務を完済した場合、譲渡担保権者と債務者が共同で、所有権移転登記の抹消登記を申請し、不動産の所有権を債務者に戻します。
・債務不履行が発生した場合、債権者は債務者に対して、担保を実行する旨を通知します。
・通知を受けた債務者は、担保物件(不動産)を債権者に引き渡します。ただし、すでに債権者の下にある場合は不要です。
・債権者は以下のいずれかの方法で清算を行います。
債権者が不動産をそのまま所有権を取得し、不動産の評価額から債権額を差し引いた差額を債務者に支払います。評価額が債権額を上回る場合、差額の清算が求められます。(帰属清算型)
裁判所に競売を申立て、競売手続きが開始されます。裁判所が不動産を差押え、競売によって換金し、その代金から債権を回収します。 (競売型)
■ まとめ
買戻特約が盛り込まれる不動産を購入される買主の注意点として次の点があげられます。
・買戻し特約の期間中は、売主の申し出があれば不動産を返還する義務が生じ、完全に所有権を確保できない。
・特約期間が満了しても、所有権移転登記の情報が自動で抹消されるわけではなく、買主自身で抹消登記の手続きを行う必要があります。
など注意しなければならないことがあります。
不安な場合、担当者へ不明な点、不安な点など確認しながら進めていただきものです。
■記事の投稿者 飯島興産有限会社 飯島 誠

私は、予想を裏切るご提案(いい意味で)と、他者(他社)を圧倒するクオリティ(良質)を約束し、あなたにも私にもハッピー(幸せ)を約束し、サプライズ(驚き)のパイオニア(先駆者)を目指しています。
1965年神奈川県藤沢市生まれ。亜細亜大学経営学部卒業。(野球部)
東急リバブル株式会社に入社し、不動産売買仲介業務を経て、その後父の経営する飯島興産有限会社にて賃貸管理から相続対策まで不動産に関する資産管理、売買仲介、賃貸管理を行う。
コラムでは不動産関連の法改正、売買、賃貸、資産管理について、実務経験をもとにわかりやすく発信しています。

●資産管理(相続・信託・後見制度)につきましては、こちらをご参照ください。
#不動産 #売買 #不動産売買 #買戻特約 #再売買の予約 #譲渡担保