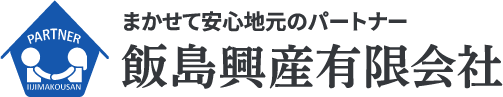■ 目次
- ■ はじめに
- ■ 注意が必要な代理行為
- ■ 代理人の確認方法
- ■ 不動産売買に関する代理人と委任状
- ■ まとめ
■ はじめに
不動産売買において、売主・買主である当事者が遠隔地に居住していたり、仕事上の都合や病気などやむを得ない事情にて売買契約の契約日に出席できず代理人を立て契約を行うことは少なからずあります。
また、相続により取得した相続人が未成年者である場合、その不動産を売却する場合には親権者である両親が代理人となる場合や不動産の名義が夫婦共有の場合でご主人が奥様を代理して契約する場合があります。
このように、不動産売買には、売主・買主である当事者がやむを得ない事情にて売買契約の契約日に出席できない場合があります。
今回は、このような代理契約の場合どのような点に注意が必要かを考えてみます。
※個人、法人どちらでも代理人となることが可能です。
■ 注意が必要な代理行為
代理行為には「双方代理」と「自己契約による代理」と言うものがあります。
この「双方代理」と「自己契約による代理」とは原則禁止されており、当事者である売主・買主があらかじめ承諾している場合に限り有効となります。ただし、リスクがないというわけではないため、「双方代理」と「自己契約による代理」を行うことは事務上ないと思われます。
双方代理
双方代理とは、不動産の売買において、Aという方が売主と買主双方の代理人として契約を締結する行為です。
双方代理が禁止されている理由は、売主は不動産の売却価格を高くしたい、と考えます。反対に買主は不動産を安く購入したい、考えます。
このように売主と買主には考え方の相違があり、利益が相反する売主と買主双方の代理を行うことは、代理人の権限で売却価格を決定することができてしまい、売主・買主どちらかに不利益を生じてしまう可能性があります。
このような事情から、双方代理は民法108条(自己契約及び双方代理)において原則禁止されています。
ただし、双方代理により締結された契約は無効となるわけではなく、売主・買主の当事者が追って承認すれば有効となります。
自己契約
自己契約とは、売主の一方から代理人として代理を受けた売買契約において、その代理人自ら買主として契約を締結することをいいます。
たとえば売主から売買契約の代理を受けたAがA自ら買主としてその対象となる不動産を購入する行為です。
このように代理人が自らの都合に合わせて売買契約に関する条件を決めることができるため、売主にとって不利益を生じる可能性があるためです。
※依頼者の許諾がある場合や確定している債権や債務について履行するものについては、禁止行為ではありません。
このような事情から、双方代理は民法108条(自己契約及び双方代理)において原則禁止されています。
■ 代理人の確認方法
代理人には、任意代理人と法定代理人があります。
その代理権の確認方法として最低限本人の意思確認、委任状及び代理人の本人確認などを行う必要があります。
これは、不動産売買の仲介を行う宅地建物取引業者がその代理権限の有無を細心の注意を払い行うことになります。
万一、確認を怠たり不備があり、売主・買主の当事者に損害を与えてしまった場合、宅地建物取引業者の注意義務違反を問われることがあります。
それだけ代理人の売買契約は、細心の注意が必要となるため、売主・買主および代理人は、宅地建物取引業者に協力のうえ、行うことが大切となります。
任意代理人
任意代理人とは、売主・買主本人が第三者に代理権を与え売買契約を締結することをいいます。
この場合の代理権の確認方法は、代理人が相手方に本人の印鑑証明書付の委任状を提示する方法となります。
しかし、本人に無断で印鑑証明書の交付手続きをすることも可能なため、必ず本人と面談のうえ、本人確認と不動産売却の意思確認及び当該代理人に委任した事実の有無を確認することになります。
※電話による確認方法もありますが、原則面談となります。
法定代理人
法定代理人とは、本人の意思にかかわらず法律の規定に基づき選任され、本人に代わって契約などの法律行為を行う代理人のことで、主に親権者、未成年後見人、成年後見人などが該当します。未成年者や判断能力が低下した人が不動産を売買する際に、本人の代わりに契約を締結する権限を持ち、本人の利益を守る役割を担います。
法定代理人には以下の3種類があります。
- 親権者(親権者)
本人が未成年である場合に、その父母が親権者として法定代理人となります。
- 未成年後見人
親権者がいない未成年者に対して、家庭裁判所が選任する代理人です。
- 成年後見人
認知症などで判断能力が低下し、自分で財産管理や法律行為を行うことが難しい成年者を保護するため、家庭裁判所が選任する代理人です。
■ 不動産売買に関する代理人と委任状
不動産の売買において代理人を立てたうえで売却や購入を行うことは可能です。
しかし、注意いただいたことは、万一売却の媒介手続きから代理人を立てて行う場合、その手続き上3種類の委任状を作成する必要があります。
通常、不動産の売却における手続きは、大きく分けて3つの手続きとなります。
① 不動産業者との媒介契約の締結時
② 買主との売買契約の締結時
③ 所有権の移転・残代金の受領・不動産の引き渡し時
以上3つの手続きの委任内容
■ 不動産業者との媒介契約の締結時
1.媒介契約の種類(一般・専任・専属専任)の選択。
2.媒介契約の期間の選択および媒介契約の更新の手続き一切
3.●●●●株式会社より媒介契約の説明を受けること。
4.媒介契約の締結。
5.これらに付帯する一切の権限。
■ 買主との売買契約の締結時
1.●●●●株式会社より重要事項説明書の説明を受けること。
2.重要事項説明書の説明を受けた旨の署名・押印
3.売主としての売買契約締結行為。
4.売買代金の(手付金を含む)の授受。
5.これらに付帯する一切の権限。
※ここでご注意いただきたいのは、令和●年●●月●●日付末尾備考の不動産売買契約(買主:株式会社 ●●●)に関する次の権限一切。というように買主名の記載を行うことです。
■ 所有権の移転・残代金の受領・不動産の引き渡し時
1.売買代金の支払い
2.売買物件の引渡ならびに所有権の移転を受けること。
3.その他上記契約に基づく義務の履行。
4. 所有権移転登記申請をすること。
5.登記申請について復代理を専任すること。
6.その他前各号に付帯する一切の件。
※ここでご注意いただきたいのは、令和●年●●月●●日付末尾備考の不動産売買契約(買主:株式会社 ●●●)に関する次の権限一切。というように買主名の記載を行うことです。
■ まとめ
不動産の売買においてやむを得ず代理人を立てたうえで行う場合には、代理権の在り方や禁止されている事項に関しての注意が必要です。
不動産の売買は大きな金額ですので、代理人を立てる場合は本当に信頼のおける方にお願いされるべきであり、相手方にも事前に代理人にて売買契約を進める旨を伝える必要もあります。
また、委任状の内容は、第三者が見ても理解できるようにしておかなければなりません。
後々のトラブルとならないように、不明な点はかならず確認するようにしていただくことをオススメします。
■記事の投稿者 飯島興産有限会社 飯島 誠

私は、予想を裏切るご提案(いい意味で)と、他者(他社)を圧倒するクオリティ(良質)を約束し、あなたにも私にもハッピー(幸せ)を約束し、サプライズ(驚き)のパイオニア(先駆者)を目指しています。
1965年神奈川県藤沢市生まれ。亜細亜大学経営学部卒業。(野球部)
東急リバブル株式会社に入社し、不動産売買仲介業務を経て、その後父の経営する飯島興産有限会社にて賃貸管理から相続対策まで不動産に関する資産管理、売買仲介、賃貸管理を行う。
コラムでは不動産関連の法改正、売買、賃貸、資産管理について、実務経験をもとにわかりやすく発信しています。

●資産管理(相続・信託・後見制度)につきましては、こちらをご参照ください。
#不動産 #売買 #不動産売買 #代理人 #双方代理 #自己契約 #委任状
#委任内容 #代理人確認方法