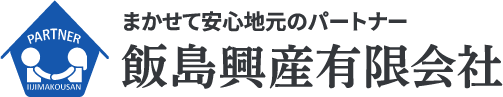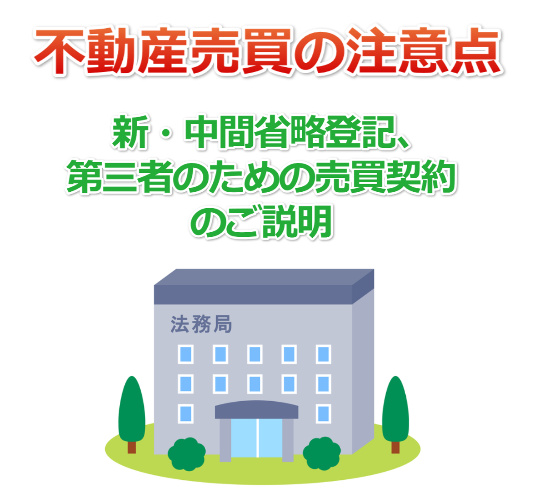
■ 目次
- ■ はじめに
- ■ 中間省略とは
- ■ 不動産登記法改正による変化
- ■ 新・中間省略登記の誕生
- ■ 新・中間省略登記の2つの違い
- ■ 新・中間省略登記における注意点
- ■ まとめ
■ はじめに
不動産の売買において所有権を移転する場合、通常は売主Aから買主Bに移転します。
しかし、不動産売買の登記には中間省略登記と言うものがあり、売主Aから買主Bへ所有権を移転せず、買主Bが転売した買主Cへ所有権を移転する方法が存在します。この手法が「中間省略」というものです。
今回は、平成17年に不動産登記法が改正され、この「中間省略」の登記方法も変わり、売主、買主共に注意しなければならない点等を考えてみます。
■ 中間省略とは
中間省略とは中間省略登記の略であり、不動産売買における一連の登記の一部省略することをいいます。
売主Aと買主Bは売買契約を行い、買主Bは自ら売主となって買主Cと売買契約を行った場合、所有権の移転は、A→Bへ移り、その後B→Cへ移転することになります。
しかし、中間にいるBは自身へ移転する登記を省略して、AからCへ直接、所有権が移転したという登記を行うことが出来るのです。
中間省略の登記のメリットは,登録免許税が1回分で済むことです。
通常であれば、所有権の移転は、A→Bへ移り、その後B→Cへ移転することになりますので登録免許税が課税対象者は、BとCとなります。また、不動産所得税が課税対象者もBとCとなります。
しかし、中間省略登記により、Bと言う存在が登記上表に現れず、Bは登録免許税を回避することが出来たのです。
※不動産取得税について
中間省略登記によりBは不動産取得税も課税されないと誤解されている方も少ない内容ですが,不動産取得税は、流通税です。
※流通税(りゅうつうぜい)とは、資産(財産)の権利移転に課税される租税となります。
国税としては、自動車重量税、印紙税、登録免許税などがあります。
登記とは全く関係なく,BがAより取得した時点とCがBより取得したでBとCに対し、課税されます。
ただし、実際には,法務局にある登記簿にはA→Cへ所有権移転の登記が記載されているのみであり、Bが現れません。この登記関係によりA→B→Cと所有権が移転した事実が隠れているため、納税を免れているだけのことです。
中間省略登記のデメリットは,ズバリ!実際の取引経過が登記に反映されないことです。
■ 不動産登記法改正による変化
平成17年3月7日に不動産登記法が改正され、従前の不動産登記法では,中間省略登記が可能であったことはお伝えしました。
では、なぜ?中間省略登記が可能であったのか、と言えば、従前の不動産登記法では,所有権の移転登記の登記申請書には、登記義務者と登記権利者とが所有権移転の原因を特定して共同申請しており、所有権移転の原因が「売買」であっても売主と買主とは記載は不要でした。
その結果、所有権は登記義務者Aから登記権利者Cに移転した売買とすることが可能となっていました。
しかし、不動産登記法改正により、登記を申請する場合、書面が変更され、新たに「登記原因証明情報」という書面の提出が必要になりました。
この「登記原因証明情報」とは、登記の原因となった事実や法律行為、これに基づく権利変動が生じたことを司法書士が売買契約書などを元に事実確認ぬえ、売主と買主が連名で署記名押印のうえ、法務局に対し、証明するものです。
よって従前の不動産登記法では可能であったA→B→Cと所有権が移転した事実を隠すことが出来なくなり、中間省略の登記が不可能となったのです。
事実、「AはCに対し、不動産を売却した」という記載の登記原因証明情報を作成すれば、事実ではなく、虚偽の登記申請であり違法行為となるのです。
■ 新・中間省略登記の誕生
以上のように、不動産登記法の改正により、正しい登記記録が保存されなくなるという観点から中間省略登記に反対していました法務局にとっては一定の結論が出ることになりました。
しかし、この結論に対し、不動産取引の現場からは大きな反発が生じたのです。
中間省略の登記は、税金の課税回避という悪いイメージがある一方、不動産証券化など、実務的に中間省略登記を利用したほうが便利なケースもあり、不動産取引活性化の阻害要因になることが問題となったのです。
この問題について内閣総理大臣の諮問機関である規制改革・民間開放推進会議は、「第三者のためにする契約」「買主の地位の移転」の2つの形態により中間省略登記と同様の効果をもたらす登記ができること答申しました(平成18年12月21日)。
その後において同会議が法務省から「第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転登記」または「買主の地位を譲渡した場合における売主から買主の地位の譲受人への直接の所有権の移転登記」という形であれば、AからCへの直接の移転登記申請が可能である旨を確認し、この回答の内容を平成19年1月12日法務省民事局から全国の法務局へ通知として伝えられており、関係省庁・団体の新・中間省略登記が適法性であることの根拠は次のとおりです。
規制改革・民間開放推進会議(内閣総理大臣の諮問機関)及び内閣
①法務省民事局民事第二課長に対し、第三者のためにする売買契約の売主から当該第三者への直接の所有権の移転の登記の申請の可否に関して、平成18年12月21日付けで照会を行い、可とする旨の回答を翌日受け取っている。
②それを受けて、同年12月25日、同推進会議第3次答申を行い、それを内閣が承認する閣議決定をしている。
法務省
①規制改革・民間開放推進会議から上記①照会に対し、平成18年12月22日、可とする回答を発した。
②また、規制改革・民間開放推進会議の答申及び閣議決定を受けて、平成19年1月10日、法務省民二第52号民事第二課長通知をもって関連諸団体に、上記回答を周知させるための通知を行っている。
日本司法書士会連合会
平成19年5月30日、会長名による通知によってこの手法を承認した。同年12月12日には「直接移転取引に関する実務上の留意点について」を全司法書士会に配布。各司法書士会はそれを会員である各司法書士に配布した。
国土交通省
「新・中間省略登記」が必ず他人物売買を伴うため、これが「宅建業法33条の2の規定に反するのではないか」という疑問を解消するために省令(宅建業法施行規則)を改正(平成19年7月10日公布・施行)し、この手法が宅建業法上も適法であり得ることを宣言した。
以上により、現在は新・中間省略登記と呼ばれる手法により中間省略登記が可能となっています。
■ 新・中間省略登記の2つの違い
「第三者のためにする契約」「買主の地位の移転」の2つの形態により中間省略登記登記方法は2種類あります。
この2つの形態については次のとおりです。
第三者のためにする契約方法
現在の売主Aと買主Bとの間にて締結する売買契約時に、買主Bが自ら売主となり、直接最後の名義人に移転できる旨の特約を記載する。
そして、買主Bから最後の名義人へ引き渡す売買契約書を締結し、買主Bが所有権移転先としてCを指定し、現在の売主AからCに所有権を直接移転することが可能となります。
※買主Bが宅地建物取引業者の場合、宅地建物取引業者の他人物売買を禁止している宅地建物取引業法33条の2に違反するのではないかとの問題もありましたが、同法施行規則の改正により、第三者のためにする売買契約の手法を用いる場合には、宅建業者による他人物売買も可能であることが明記されました。
買主の地位を譲渡する方法
現在の売主Aと買主Bとの間にて締結する売買契約をします。そして、買主Bが持つ買主のの地位を最後の名義人に譲渡する契約を交わすことで登記を省略することができます。
※以上のような第三者に向けた売買契約を担う不動産業者を「三為(さんため)業者」と呼びます。
■ 新・中間省略登記における注意点
新・中間省略登記を活用する場合は、買主の地位の譲渡する契約に注意が必要です。
一般的に不動産の売買契約を締結する場合、宅地建物取引業者には宅地建物取引業法により重要事項説明の義務と契約不適合責任を負う義務が課せられています。
しかし、買主の地位を第三者へと譲渡する場合は、現在の売主Aから最後の名義人との間にて締結する契約形態となります。
その場合、売買契約として買主の地位を第三者へと譲渡する形態であれば宅地建物取引業法により重要事項説明の義務と契約不適合責任を負う義務が生じますが、「譲渡」契約の場合、宅地建物取引業法により重要事項説明の義務と契約不適合責任を負う義務が生じないということになります。
また、現在の売主A、中間者である買主Bが契約不適合責任を免責する特約を盛り込んでいれば、契約不適合責任を負わなくて済む場合がありますので注意が必要です。
■ まとめ
新・中間省略登記において、現在の売主Aは中間者である買主Bと契約を締結した場合、買主Bが自ら売主となり、買主Cとの間にて売買契約を結ばない限り決済されない、と言われる方がおいでになりますが、現在の売主Aは買主Bの利益のために売却するわけではなく、買主Bに協力するのみです。
つまり、買主Bは、買主が見つかる、見つからないは関係なく、残代金の支払いを売買契約の期日に支払うことを明確にすることが大切です。
このように新・中間省略において問題点を把握のうえ、売買契約を締結していただき、万一不明な場合には専門家にご相談をいただくことをオススメします。
■記事の投稿者 飯島興産有限会社 飯島 誠

私は、予想を裏切るご提案(いい意味で)と、他者(他社)を圧倒するクオリティ(良質)を約束し、あなたにも私にもハッピー(幸せ)を約束し、サプライズ(驚き)のパイオニア(先駆者)を目指しています。
1965年神奈川県藤沢市生まれ。亜細亜大学経営学部卒業。(野球部)
東急リバブル株式会社に入社し、不動産売買仲介業務を経て、その後父の経営する飯島興産有限会社にて賃貸管理から相続対策まで不動産に関する資産管理、売買仲介、賃貸管理を行う。
コラムでは不動産関連の法改正、売買、賃貸、資産管理について、実務経験をもとにわかりやすく発信しています。

●資産管理(相続・信託・後見制度)につきましては、こちらをご参照ください。
#不動産 #売買 #不動産売買 #手付金 #内金 #残代金 #現金 #預金小切手 #振込 #不動産売買の注意点 #瑕疵担保責任 #契約不適合責任 #設備表 #物件状況等説明書 #経費 #諸経費 #印紙代 #登録免許税 #司法書士報酬額 #測量代 #越境 #損害賠償請求 #建築不可 #売却 #売出価格 #成約価格 #販売活動 #販売スケジュール #不動産会社の選定 #囲い込み #専任媒介契約 #専属専任契約 #一般媒介契約 #リースバック #リースバック契約 #リバースモーゲージ #メリット #デメリット #第三者 #占有 #第三者の占有 #オーナーチェンジ #不動産の表示 #目的物の表示 #土地 #建物 #区分所有建物 #マンション #地中埋設物 #産業廃棄物 #任意売却 #競売 #住宅ローン #売主死亡 #買主死亡 #登記申請方法 #中間省略 #問題点 #注意事項