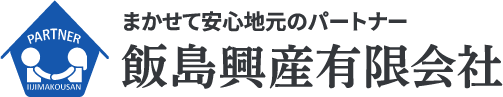■ 目次
- ■ はじめに
- ■ 接道義務とは
- ■ 接道義務に違反した場合
- ■ 接道義務が必要な理由
- ■ 接道の長さとは
- ■ まとめ
■ はじめに
不動産の売買において「敷地は道路に最低2メートル以上接していないといけない」と聞いたことがあると思います。
この「2メートル以上接していないといけない」を接道義務といいます。
接道義務とは、建築基準法で定められている道路と敷地に関する規定のことです。
この接道義務を満たしていない土地は原則として建物を建築することができない土地です。
今回は、この「接道義務(接道の長さ)」についてどのような接道であれば問題が生じないのか、など注意点を含めて考えていきます。
■ 接道義務とは
接道義務とは、敷地に建物を建てる場合に、建築基準法に定められた道路に2メートル以上接していなければならないという決まりのことです。
路地状敷地の土地でも、道路に面する通路の間口が2メートル以上あることが求められます。
【建築基準法】
(敷地等と道路との関係)
第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
※建築基準法に定められた道路
1 道路法による道路で幅員が4m以上のもの
2 都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいてつくられた幅員4m以上のもの
3 建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に幅員4m以上あったもの
4 道路法や都市計画法等によらないで築造する道で、その位置の指定を受けた幅員4m以上のもの
5 建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に、その道に沿って、建築物が建ち並んでいた幅員
1.8m以上4m未満のもの(通称「2項道路」と呼んでいます。)
※ 1以外は公道、私道の両方の場合があります。
■ 接道義務に違反した場合
接道義務違反であっても罰則等が発生するわけではありません。
接道義務違反に抵触する場合、建物の建築が原則出来ない、と言うことです。
※周囲に広い空地があり交通・安全・防火・衛生上、問題ないと認められれば再建築が可能になる場合があります。
万一、接道義務違反に抵触している場合、現在において土地に建物が現存している場合は、増築や再建築は禁止されています。
また、接道義務に違反すると、建築中であっても工事の停止を命じられます。
【建築基準法】
(違反建築物に対する措置)
第9条 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
■ 接道義務が必要な理由
建築基準法により接道義務が規定されたのは1950年(昭和25年)からです。
この接道義務の目的は、安全対策であり、緊急車両の通行を確保するためと災害時の避難路を確保するためです。
万一、火災が発生した場合、消防ポンプ車が現場にたどり着けるか、否かと言うことは大切なことです。
一般的な消防ポンプ車の幅は約2.0メートル、救急車の幅は、約1.9メートル、大型のはしご車で約2.5mです。
接道義務により2メートルを確保することにより、緊急車両の通行を確保できることになります。
※建築基準法の第42条で「道路」の幅員が4メートル(指定区域内では6メートル)と規定されているのは、消防車の幅2.5メートルプラス活動スペースを1メートルとした場合の幅となっています。
また、予期せぬ災害の場合、接道義務で最低2メートル確保することで、災害時の避難経路として確保することも目的となっております。
■ 接道の長さとは
敷地の接道の長さとはどこの部分なのでしょうか。
たとえば次のような敷地があったとします。それぞれの敷地の接道の長さを明示しましたのでご確認ください。
ケース①
この場合、接道の長さはAの長さをいいます。

ケース②
ケース①の場合同様の間口の敷地で間口部分にフェンス塀を構築している場合、敷地と道路は有効に接続しているとの考え方のうえ、接道長さはAの長さをいいます。
この場合のBの長さは、常識的に人が出入りできる幅である1メートル内外であれば有効な接道として認められます。

また、図2-1のとおり、道路境界線や隣地境界線に擁壁やブロック等の構造物が設置されていても、敷地が法上の道路に2メートル以上接しており、かつ、現に法上の道路への通行が可能であれば、接道義務を満たしている判断されます。

ケース③
不生計地の場合、接道の長さはCの長さをいいます。安全上の観点から、建築物の敷地は敷地内から道路に有効に接続する必要があるため、A+Bの長さではなく、Cの長さとなります。
※各市区町村にて条例で必要な長さを定めている場合もありますので確認は必要です。

ケース④
路地状敷地の場合、接道の長さは、図4の場合には、AまたはB、図5の場合には、Aの長さをいいます。
この場合も安全上の観点から、建築物の敷地は敷地内から道路に有効に接続する必要があるため、図4の場合、A+Bが2メートル以上であっても、A・Bどちらかが2メートル未満の場合には「道路に有効に接続している」とは言えず、接道義務違反となります。
また、図5のような路地状敷地の場合、建築物の敷地は敷地内から道路に有効に接続する必要があるため、路地状敷地部分の一部が2メートル未満の場合には「道路に有効に接続している」とは言えず、接道義務違反となります。


ケース⑤
道路と敷地に高低差があり、建築物から道路に通じる階段や傾斜路等の有効な通路等が設けられていない場合、敷地が法上の道路に接しているとはいえません。
この場合、敷地内に道路に通じる階段や傾斜路等の有効な通路を設ける必要が生じます。なお、階段や傾斜路等の有効幅は2メートル以上でなくても、避難上支障のない幅員であれば良いとされています。

ケース⑥
行き止まりになっている法42条2項道路(狭あい道路)の終端に接する敷地の長さは、現況の幅員が4メートル未満の場合でも、原則道路の中心線から2メートル後退した線を道路境界線とみなして判断されます。


法42条2項道路(狭あい道路)の接する敷地の長さは、現況の幅員が4メートル未満の場合でも、原則道路の中心線から2メートル後退した線を道路境界線とみなして判断されます。

■ まとめ
接道義務とは、敷地に建物を建築する場合、建築基準法に定められた道路に2メートル以上接していなければいけないという規定です。
接道義務は、災害時の避難路や緊急車両の通行を確保するため、接道義務を満たしていない場合、工事の停止や再建築を命じられる場合があります。
接道義務は、特殊な敷地の場合、各市町村町により違いが生ずる場合もあり、適切に指示を受ける必要がありますのでトラブルのないゆ専門家に相談のうえ、売買を行っていただくことをオススメします。
■記事の投稿者 飯島興産有限会社 飯島 誠

私は、予想を裏切るご提案(いい意味で)と、他者(他社)を圧倒するクオリティ(良質)を約束し、あなたにも私にもハッピー(幸せ)を約束し、サプライズ(驚き)のパイオニア(先駆者)を目指しています。
1965年神奈川県藤沢市生まれ。亜細亜大学経営学部卒業。(野球部)
東急リバブル株式会社に入社し、不動産売買仲介業務を経て、その後父の経営する飯島興産有限会社にて賃貸管理から相続対策まで不動産に関する資産管理、売買仲介、賃貸管理を行う。
コラムでは不動産関連の法改正、売買、賃貸、資産管理について、実務経験をもとにわかりやすく発信しています。

●資産管理(相続・信託・後見制度)につきましては、こちらをご参照ください。
#不動産 #売買 #不動産売買 #道路 #接道 #接道義務 #建築基準法 #道路と敷地 #接道の長さ #間口 #建築基準法の道路 #建築基準法第43条第1項